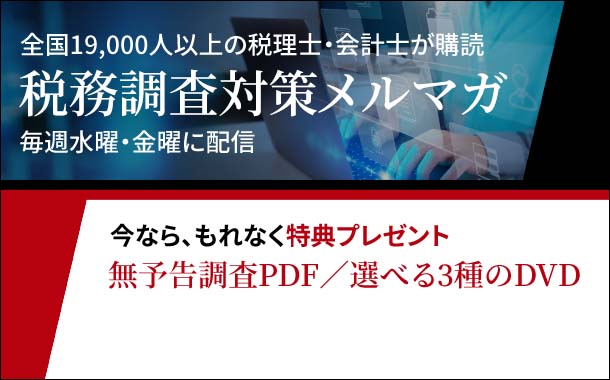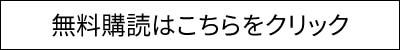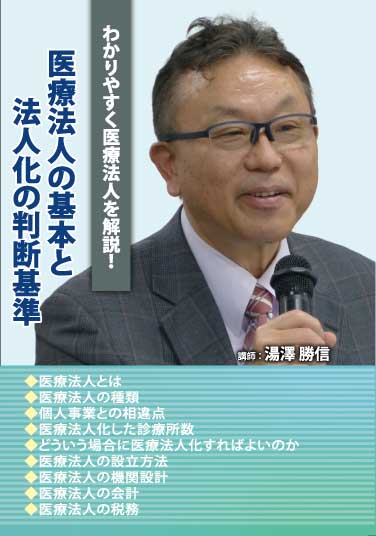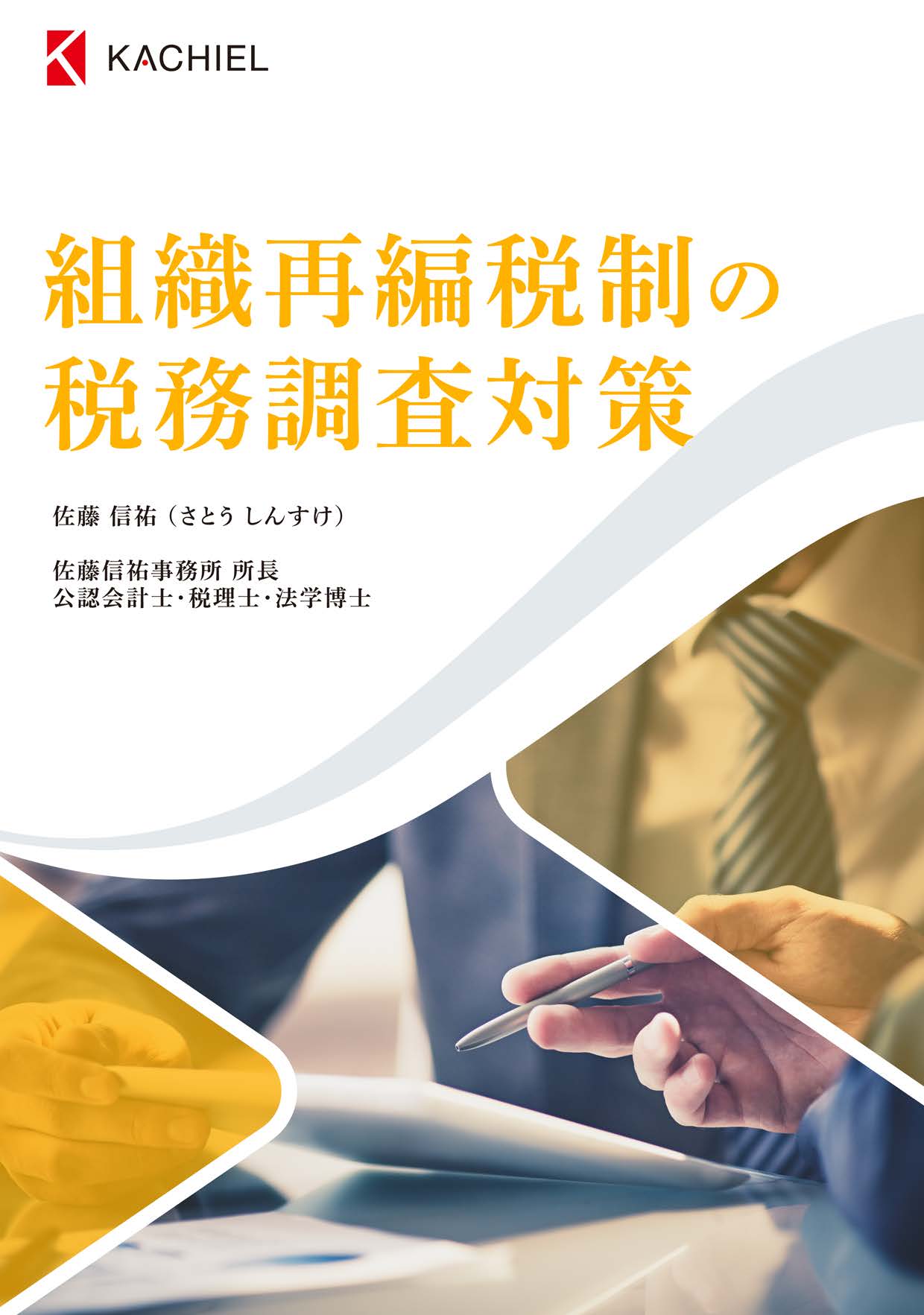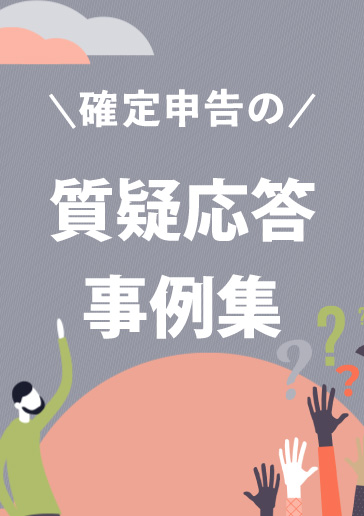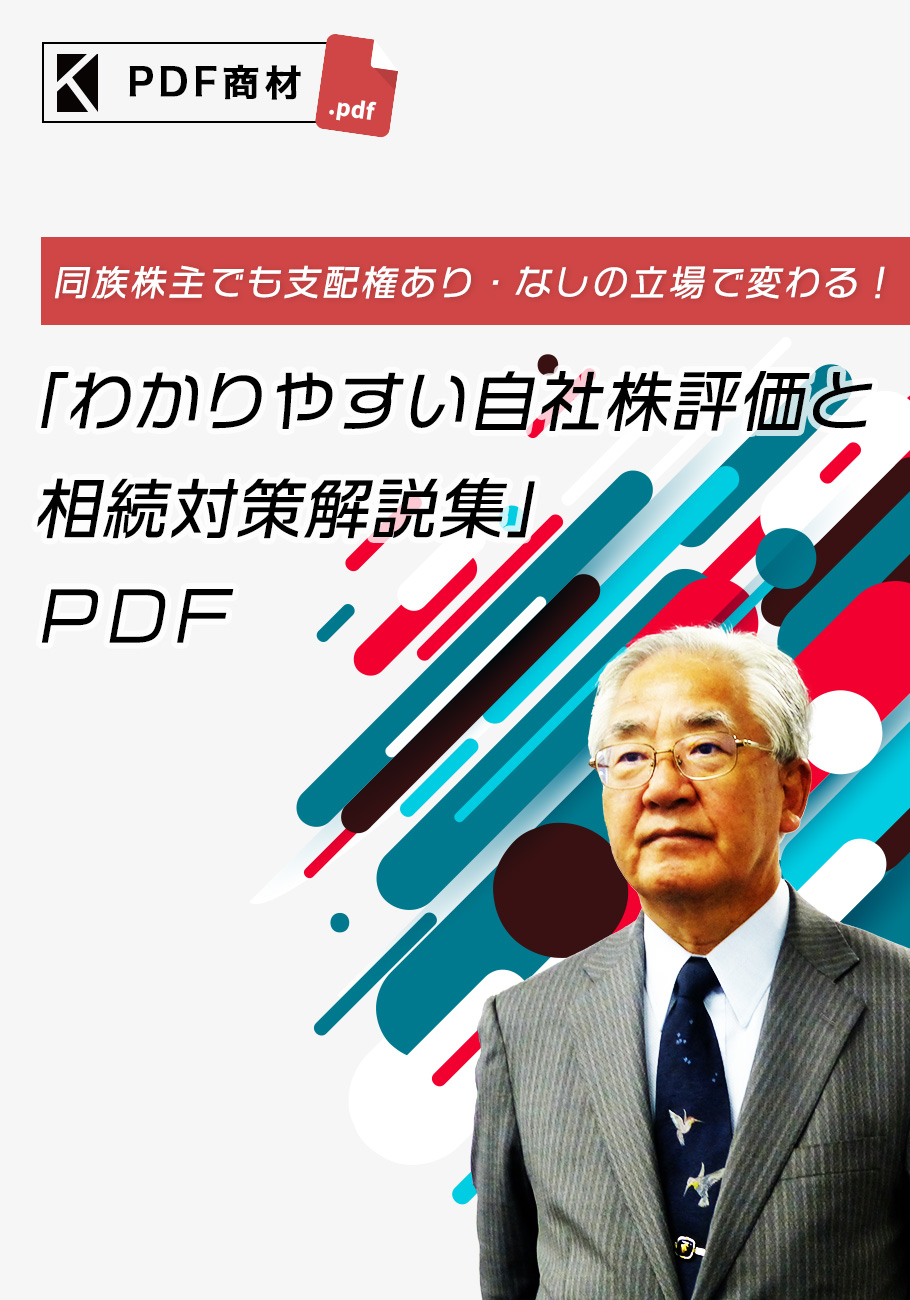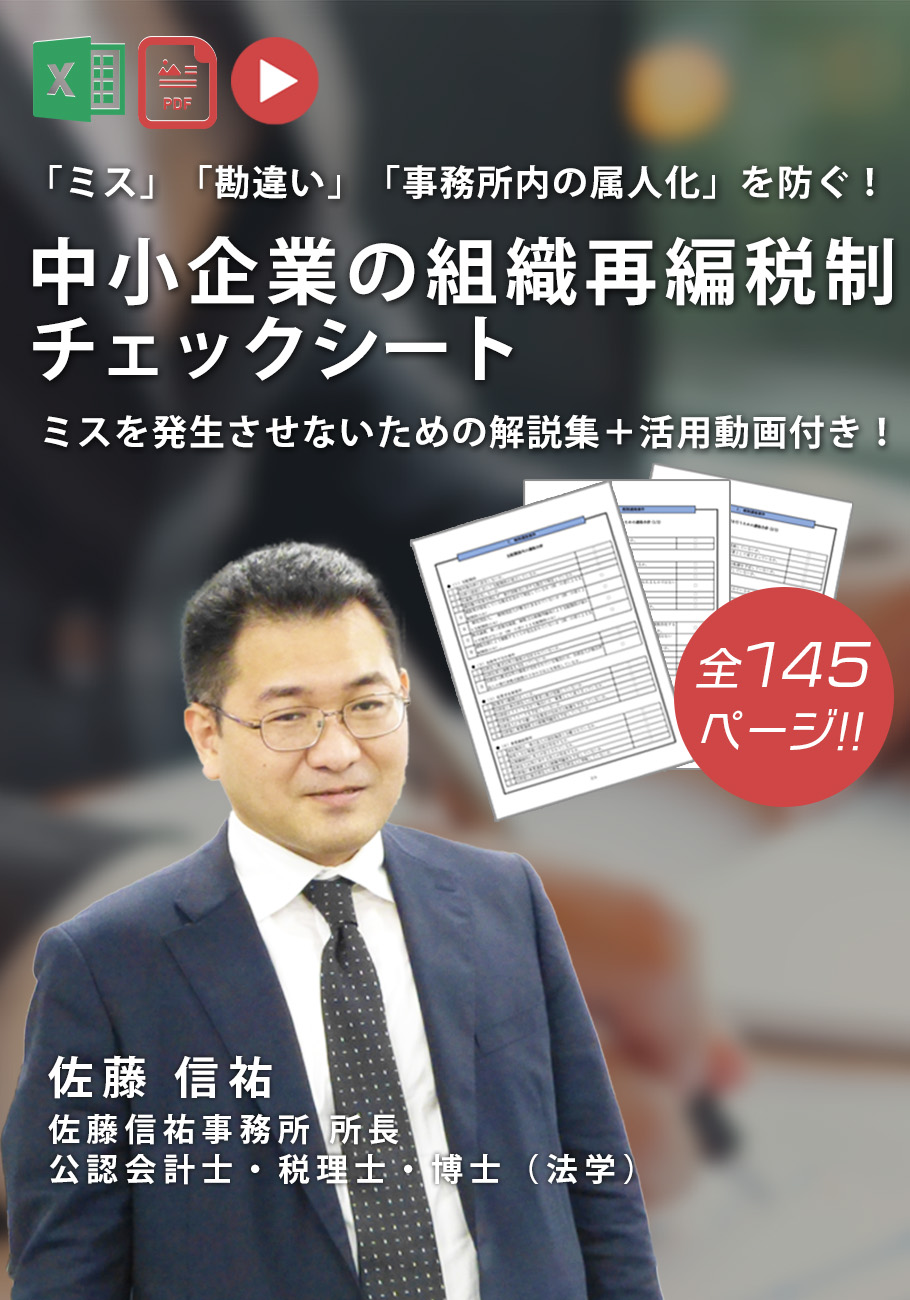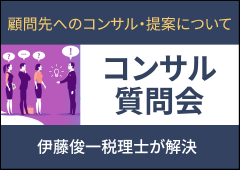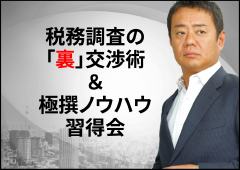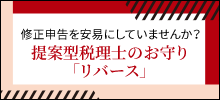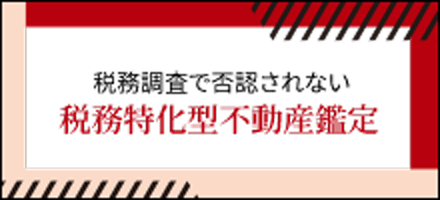KACHIEL(カチエル)は
税理士向けセミナーの開催や教材販売、
知識共有を促すメーリングリストの
提供等を通じ、
ビジネスの飛躍を
サポートしています。
Seminar
参加受付中のセミナー
税務・法務・税務調査対策等、様々なテーマで
年間数十回の税理士向けセミナーを開催中。
すべてのセミナーが受け放題になる
「KACHIEL税務アカデミー」も好評です。
| 日時 | セミナータイトル | 講師 |
|---|---|---|
| オンデマンド | \簿記や税理士試験のお勉強知識だけでは足りない!/ 事務所全体のミス・賠償リスクを減らす 「税務会計“実務力”トレーニング」 TAXWISE説明会 |
瀬戸 貴史(せと たかし) 山岡 良輔(やまおか りょうすけ) 株式会社KACHIEL |
| 2024年5月1日(水) 18:00~20:00(開場17:30) ※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。 |
~銀行が見ているポイントから考える~ 顧問先に喜ばれる銀行融資支援 |
赤沼 慎太郎(あかぬま しんたろう) アクティス株式会社/行政書士赤沼法務事務所 代表、経営コンサルタント、行政書士 |
公開日:2024年5月7日(火) |
《職員向け》 |
脇田 弥輝(わきた みき) |
| 2024年5月9日(木) 17:00~18:00 |
~コスパ最高!税理士・会計事務所のための職員採用~ 「新・セレクト!」サービス説明会 |
大竹 邦明(おおたけ くにあき) 株式会社KACHIEL |
Educational material
税理士向け教材
過去に開催されたセミナーの
DVDや業務に役立つPDF等を提供中。
すべてのセミナーDVDが事務所に届く
「KACHIEL税務アカデミープレミアム」も
好評です。
Service&Tool
税理士向けサービス・ツール
税理士同士で問題解決する
メーリングリストをはじめ、AIによる仕訳ツール、
低コストの採用支援サービス等、
税理士事務所のあらゆるシーンを
支援するサービス・ツールを提供しています。