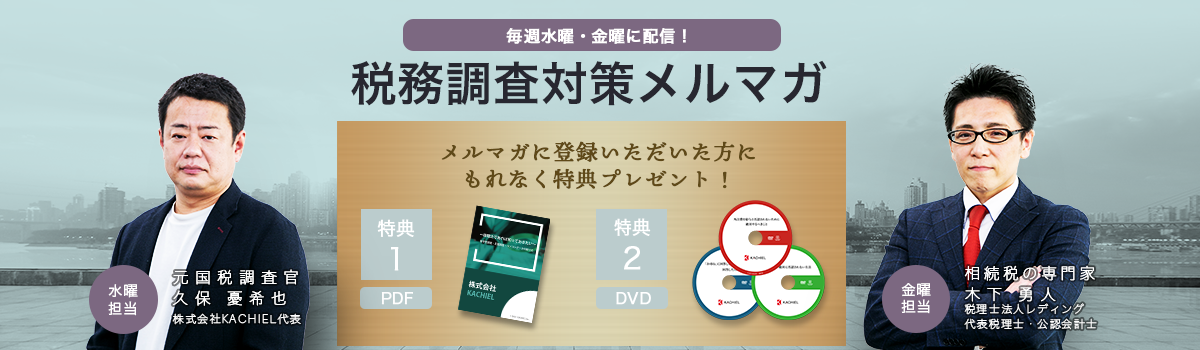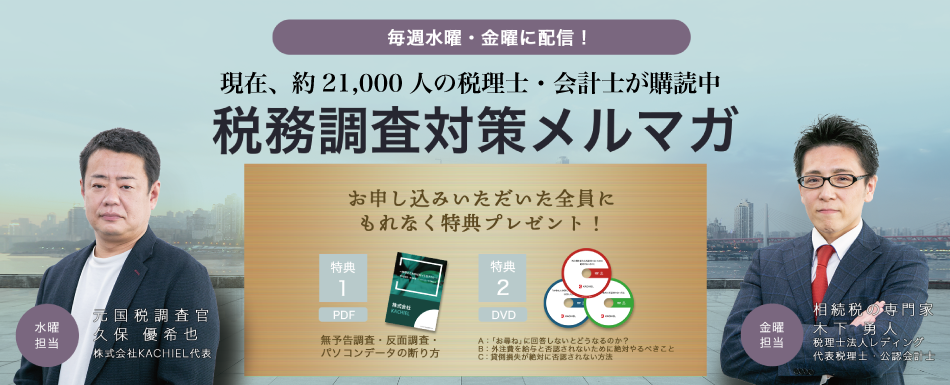裏金は誰に帰属するのか?(その1)
※2017年10月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「裏金は誰に帰属するのか?(その1)」ですが、
仙台地裁(平成24年2月29日判決)を取り上げます。
このシリーズを来週金曜日、再来週の金曜日とつづけ、
3回もので配信します。
では、この事案の概要及び前提事実です。
○旅館業及び飲食業などを営む会社
○平成19年9月ないし12月ころに原告の帳簿書類が調査された
○平成12年5月1日から平成18年4月30日までの6年間にわたる
各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の間に、原告の従業員らが
関係業者からいわゆるリベートとして受領していた手数料合計9786万
3000円(以下「本件手数料」という。)に関し、そのうち平成12年
5月1日から平成13年4月30日までの事業年度(以下「平成13年4月期」
という。)に受領した手数料609万9000円を総勘定元帳の雑収入科目に
計上しなかった
○青色申告の取消し、法人税及び消費税に対する更正処分、重加算税の賦課
決定がされた
○訴外乙(以下「訴外乙」という。)は、平成8年10月1日に原告に入社
した後、和食、洋食及び中華料理部門の総責任者である調理部調理課長等を
歴任した後、平成18年9月21日には副総支配人(営業部、料飲部担当、
料飲部支配人、料飲課長等兼務)に就任するとともに、調理部支配人の職を
解かれ、その後、平成19年12月20日付けで原告を退職した
○訴外丙(以下「訴外丙」といい、訴外乙と総称して「訴外乙ら」という。)
は、平成16年11月4日に原告に入社した後、平成17年2月21日付けで
訴外乙の後任として調理部和食調理課長に、平成18年9月21日付けで
同じく和食調理部支配人(和食調理課長兼務)に就任し、平成19年8月
21日付けで総料理長(和食調理長兼務)に就任した
○有限会社E(以下「訴外会社」という。)は、加工食品の製造販売等を目的
とする法人であり、有限会社Cを通じて、本件各事業年度において原告に食材
を納入していた株式会社Dに本件食材を納入していた
○訴外会社が、訴外乙に対し、本件食材納入時に訴外乙からの指示に基づいて
いわゆるリベート分を上乗せした価格で取引を行い、納入後の代金から
リベート分を訴外乙に渡すという形で本件手数料を支払っていた
○本件手数料の額は、下記の通り
・平成13年4月期:609万9000円
・平成14年4月期:1211万4000円
・平成15年4月期:1507万3000円
・平成16年4月期:2109万3000円
・これらは全て、訴外乙の受領分
・平成17年4月期:2226万6000円
訴外乙の受領分が1982万7000円
訴外丙の受領分が243万9000円
・平成18年4月期:2121万8000円
訴外乙の受領分が526万円
訴外丙の受領分が1595万8000円
この前提の下、争われた訳ですが、争点は下記3点です。
○争点1、本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否か
○争点2、本件手数料が原告に帰属するとした場合、その額はいくらか
○争点3、原告による仮装又は隠ぺい行為の有無
そして、仙台地裁は下記と判断したのでした。
○本件各処分は、本件手数料に係る収益が原告に帰属することを前提に、
訴外乙らが本件手数料を横領したことを理由にしているものであるから、
本件手数料に係る収益が原告に帰属したといえない場合には、訴外乙らによる
横領はその前提を欠くこととなり、原告の訴外乙らに対する損害賠償請求権も
発生しなくなる結果、原告には本件手数料相当額の益金等が生じない
○収益の帰属について、法人税法11条が、法律上収益が帰属する者が単なる
名義人であって、それ以外の者が実質的に収益を享受する場合に、その者を
収益の帰属主体とする旨を定め、消費税法13条も同様の規定を設けている
趣旨(実質所得者課税の原則)に鑑みれば、本件手数料に係る収益が原告に
帰属するか否かの判断に当たっては、本件手数料を受領した訴外乙らの法律上
の地位、権限について検討するとともに、訴外乙らを単なる名義人として
実質的には原告が本件手数料を受領していると見ることができるか否かを検討
することが相当である
○原告においては、本件食材の仕入れに関して入札制度を採用し、総務部仕入
課仕入係が発注業務を担当しているため、調理場から直接納入業者に発注を
することは禁止されており、調理部調理課に所属する訴外乙らに仕入業者の
選定権限や仕入金額の決定権限は付与されていなかった
○本件食材の仕入れに係る入札制度は、訴外会社以外の業者が入札しなく
なったため、事実上行われなくなった
○原告においては、就業規則上、「会社の許可なく、職務上の地位を利用して、
外部の者から金品等のもてなしを不当に受けた時」は解雇する旨の規定がある
ほか、訴外乙らを含む従業員にもリベートの受領が禁止されている旨が周知
されていた
○訴外乙らは、訴外会社の代表取締役(以下、「訴外丁」という。)から
リベートを受領するに際し、塩竈市やF町等、旅館の建物からは離れた所在地
にある飲食店の、あまり人目につかないような場所で授受を行っていた
○訴外乙らは、受領した本件手数料を部下との食事会やコンペ等に費消して
いたほか、原告の指示なく、自らの判断で旅館における備品等の購入に充てて
いた
○本件手数料は、原告における本件食材の仕入れに関して授受されていたもの
であるところ、原告における本件食材の仕入れに関しては入札制度が設けられ
ていることや、仕入課仕入係に発注権限が存在しており、調理課に所属する
訴外乙らには本件食材の発注権限がないことからすれば、訴外乙らが、本件
食材の仕入れに関する決定権限を原告から与えられていたとは認められない
○これらの事実に加え、原告においては、就業規則上もリベートの受領が禁止
されており、訴外乙らを含む従業員にその旨周知されていたこと、訴外乙らは、
訴外丁からリベートを受領する際、塩竈市やF町等、旅館の建物からは離れた
所在地にある飲食店の、あまり人目につかないような場所で授受を行っていた
ことなどを併せ考えると、訴外乙らが、本件食材の仕入れに関して授受されて
いた本件手数料について、原告から法的な受領権限を与えられていたと認める
ことはできない
○訴外乙らは、個人としての法的地位に基づき訴外丁から本件手数料を自ら
受け取ったものと認められるところ、自己の判断により、受領した本件手数料
を費消していたというのであるから、訴外乙らが単なる名義人として本件
手数料を受領していたとは認め難い
○本件手数料に係る収益は原告に帰属するものとは認められない
○被告は、原告における本件食材に係る入札制度は機能しておらず、訴外乙ら
が本件食材の納入業者の選定及び購入価格の決定に関して広範かつ包括的な
権限を有していたとして、本件手数料に係る収益が原告に帰属する旨主張
するが、上記の認定事実によれば、本件食材の仕入れに係る入札制度は、当時、
他の業者が入札しなくなったとの理由により事実上機能しなくなっていた
ものの、このことによって本件食材の仕入れに関する決定権限が原告の仕入
課仕入係から訴外乙らに移ったと見ることはできないから、被告の主張は採用
できない
○被告は、訴外乙らの食材の仕入れに関する決定権限を根拠付ける事実として、
訴外乙らが拡大役員会議等に出席していたことを主張するが、その主張に係る
事実から、訴外乙らが、食材の仕入れに関し、意見の具申の範囲を超えて、
決定権まで認められていたと見ることはできないから、被告の上記主張も採用
できない
○訴外乙らは、客観的に見て、本件食材の仕入れに関する決定権限や本件
手数料の受領権限を有していたとは認め難いから、訴外会社に、被告が主張
するような意図があったとしても、そのことから、上記権限に関する認定が
左右されるものではない
○本件手数料が高額であるとの指摘について見ても、本件各事業年度当時、
原告の経営成績は著しく悪化していて金融機関との取引上も、経費を過大に
計上するような余裕はなく、むしろ減価償却費の計上を一部にとどめていた
ことに照らせば、原告が、自社に帰属すべき高額の手数料収入について、
訴外乙ら個人による費消を認めるとは考え難いから、本件手数料が高額である
ことが、上記結論を左右するものとはいい難い
○被告は、原告代表者による本件手数料受領に関する対応策が不十分である
ことや、原告代表者の訴外乙らに対する発言などを根拠に、原告代表者が、
訴外乙らによる本件手数料の受領を黙認していた旨主張するが、訴外乙らが、
自らのリベート受領については、原告代表者に知られていなかったと思う旨
供述し、原告代表者も、原告の業務の詳細を直接把握していたわけではなく、
訴外乙らが上記リベートを受領していたことを知らなかった旨供述している
ことに加え、先に見たとおり、本件各事業年度当時、原告は、経営成績悪化
の状態にあったことから、リベートの金額の分だけ食材の仕入れ額(費用)を
過大に計上するような必要も余裕もなかったと見られること、原告における
懲戒の種類及び程度については、就業規則上も懲戒解雇のほかに諭旨退職など
が規定されており、情状に応じた対応が認められていること、訴外丙に対する
処分は現在も留保されている状態であることに照らせば、被告が指摘する事実
を踏まえても、原告代表者が訴外乙らによる本件手数料の受領を知って、
これを黙認していたと認めるには足りないというべきである
○被告は、訴外乙らが本件手数料の一部を原告の備品等の購入に充てていた
事実があるとして、本件手数料に係る収益が原告に帰属する旨主張するが、
上記購入行為が原告の指示なく行われていたものである以上、上記備品等の
購入は、訴外乙らが自らに帰属した本件手数料の使途を自己の判断に基づき
決定したことによるものであって、結果的に原告の利益になった部分があった
としても、そのことから、訴外乙らが単なる名義人として、訴外会社から本件
手数料を受領したものということはできないから、被告の上記主張も採用でき
ない。
○本件手数料に係る収益が原告に帰属するとは認められず、原告が訴外乙らに
対して損害賠償請求権を有しない結果、原告については、本件手数料相当額の
益金等が存在しないことになるから、本件各処分には取消事由となる違法が
あるというべきである
○その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がある
からこれらを認容する
いかがでしょうか?
この論点は「法人の行為と同視すること」ができるか否かの判断が
大きなポイントになりますが、それは
○事前に不正を防止する手段を講じていたか?
○一般的な注意義務を果たせば、防止できた状況か?
○不正をした者の職制
などにより、判断されることになります。
どんな会社でも従業員等の不正行為は起こり得ることであり、
それが税務調査で発覚することがあります。
ただし、その場合はその収益が法人に帰属するのかどうか?
という次の論点があるのです。
しかし、このようなケースにおいては「法人の収益である」と
否認指摘されることが多い訳ですが、それは事実認定次第です。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。