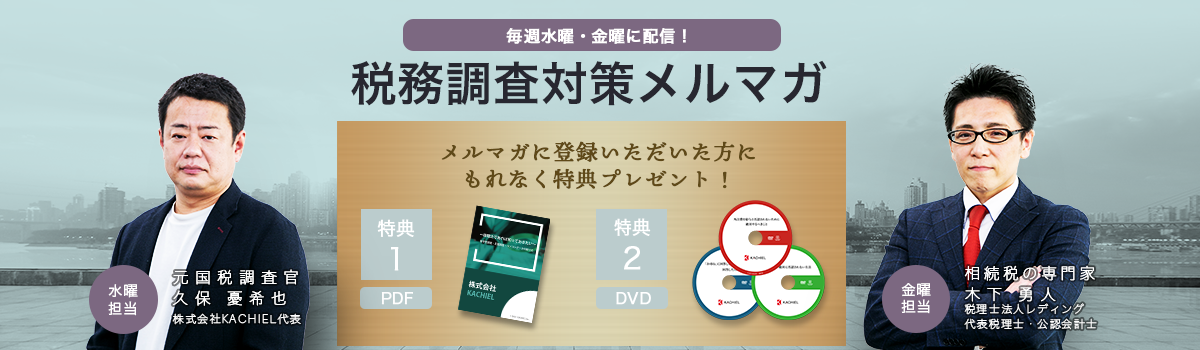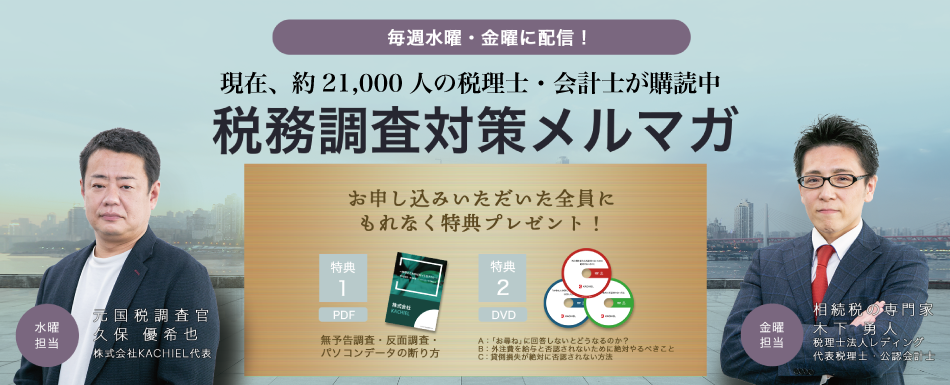保険料が定期同額給与になる場合の注意点
※2016年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「保険料が定期同額給与になる場合の注意点」ですが、
裁決(平成15年2月20日)をご紹介します。
前回、逆養老保険などの保険料が給与に該当する場合で、
それが年払いであっても役員賞与には該当せず、定期同額給与の範疇に
入る旨を解説しました。
ただし、保険料の年払いは期末ですることが多いことから、
それが「いつの損金であるのか?」ということが次の論点になります。
もし、これが保険料を支払った期の損金であるならば、
役員報酬に関し、短期前払費用の適用が可能ということになります。
上記裁決は定期同額給与という制度が導入される前のものですが、
役員報酬につき、「社会保険料等として控除する金額を差し引いた
残額の12分の1を額面金額とする12枚の約束手形を振り出して
支給した。」という事案です。
これに関し、国税不服審判所は下記と判断しました。
〇請求人が本件各役員報酬等をその支払事業年度である本件各事業年度の
損金の額に算入するためには、本件各事業年度終了の日までに確定債務
3要件すべてを充足しなければならないところ、本件取決めによっても、
辞任や退職等によって労務の提供等がされない場合には、役員報酬等の
支払義務が生じないことと定められていることからしても、後記Dの
金額を除いた本件各役員報酬等は、それぞれ本件各事業年度の翌事業年度に
おいて役務の提供等を受けることを具体的な給付をすべき原因として支出
されたものであるから、給付原因発生要件を充足しているとは認められない。
〇請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した
本件各役員報酬等の金額は、後記Dの金額を除いて、それぞれ平成10年
4月期及び平成11年4月期の各事業年度終了の日までに、当該事業年度の
損金の額に算入すべき債務が確定しているものとは認められないので、
具体的に役務の提供等を受けた事業年度の損金の額に算入すべきである。
〇本件各役員報酬は請求人の業務を執行したことに対する対価として、
本件各給料及び本件各賞与は請求人の指揮命令の下に労務を提供したこと
に対する対価として、それぞれ支払われるものであって、このような
人件費は、企業が営利活動を行う上で必要なものであり、企業活動の
根幹に係る行為に対する対価であることからすると、会計科目としての
重要性を有するといえる。
〇請求人の本件各事業年度の申告所得金額に対する人件費(請求人が
決算書に記載している「給与」金額をいい、以下同じ。)の割合は、
おおむね314.3ないし853.2%、売上金額に対する人件費の割合は、
おおむね52.5ないし56.3%で、本件各事業年度に係る人件費
のうちに本件各役員報酬等の金額が占める割合も、おおむね31.0ないし
40.7%と、高率かつ可変的であり、金額的にみても重要性を有すると
いえる。
〇本件各役員報酬等は、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化される
ような重要性の乏しい費用とは本質的にその性質を異にするものであると
認められ、本件各役員報酬等に対して、本件前払通達の後段の取扱いを
適用することはできないと解するのが相当である。
なお、これは本裁決で判断された考え方ではありませんが、
短期前払費用の対象となる役務は等質等量である必要があります。
これは東京地裁(平成19年6月29日)、裁決(平成16年3月24日)
でも示されています。
当然、役員が会社に提供する役務は等質等量にはなり得ませんので、
これにも反することになります。
逆養老保険などの給与部分については、一括で損金経理をしている場合が
多いかと思いますが、厳密に言えば、短期前払費用の適用はできないと
考えますので、ご注意ください。
もっとも、否認された事例を聞いたことがありませんので、
実務上は問題になりにくいのでしょうが。
なお、この論点には続きがありますので、次回解説します。