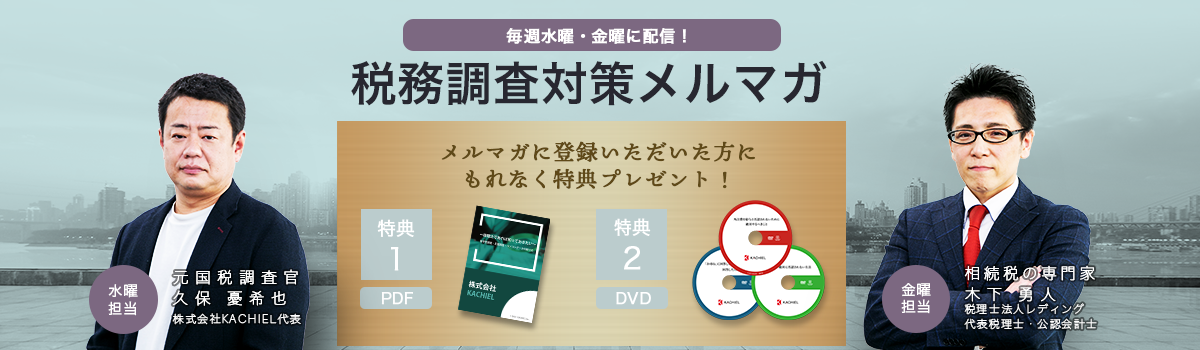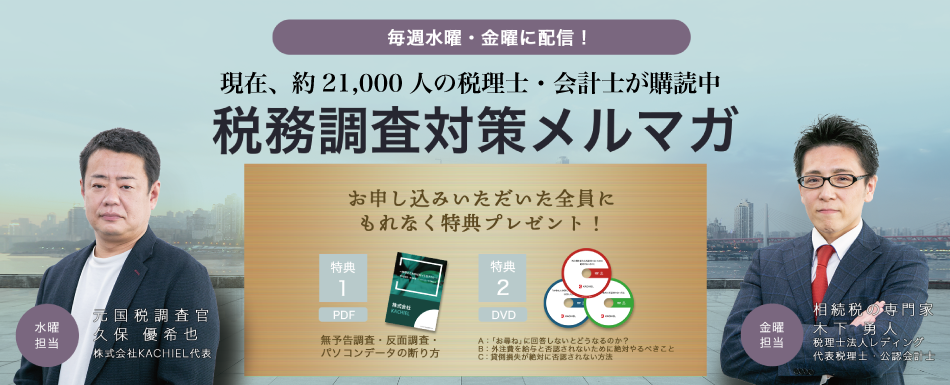妻が管理していた妻名義の預金は相続財産なのか?
※2014年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
おはようございます。税理士の見田村元宣です。
さて、今回は「妻が管理していた妻名義の預金は相続財産なのか?」ですが、平成20年10月17日の東京地裁の判決(平成21年4月16日、東京高裁にて棄却(納税者敗訴)、確定)を取り上げます。
贈与された資産は受贈者の財産であり、受贈者が管理すべきものとなります。
しかし、妻名義の預金を妻が管理していたにも関わらず、妻の財産ではなく、被相続人(亡夫)の相続財産と認定された事例が上記判決です。
具体的な前提条件は下記となっています。
○ 被相続人Aは先妻Bと婚姻後、子供C、Dが生まれた(C、Dが本件における原告)
○ AはBと離婚後、後妻Eと結婚
○ Aは遺言を残しており、「私の全財産を妻のEに相続させる」旨の記載がされていた
○ C、DはEに遺留分の減殺請求をした
○ C、DはEに遺産分割調停の申立てをし、この調停はEがC、Dに対し、遺留分の弁償として一定の財産を譲渡する旨等の調停条項を定めて成立
→ 本件において問題となった後妻E名義の預金は含まれていない
○ 後日の税務調査で、Eが管理しているE名義の預金が相続財産として更正されたが、この預金はEの財産であるとして、訴訟に至った
この前提の中、東京地裁は下記と判断したのでした。
○ ある財産が被相続人以外の者の名義となっていたとしても、当該財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったと認められるものであれば、当該財産は相続税の課税の対象となる相続財産となる。
○ 被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である。
○ 財産の帰属の判定において、一般的には、当該財産の名義がだれであるかは重要な一要素となり得るものではある。しかしながら、我が国においては、夫が自己の財産を、自己の扶養する妻名義の預金等の形態で保有するのも珍しいことではないというのが公知の事実であるから、本件E名義預金等の帰属の判定において、それがE名義であることの一事をもってEの所有であると断ずることはできず、諸般の事情を総合的に考慮してこれを決する必要があるというべきである。
○ CとDは、E名義預金等の管理及び運用はEがしていた旨主張するところ、
①本件E名義預金等について、取引に係る書類の記入や実際の手続をしていたのはEであること、②EはAが脳こうそくで入院した後においても、E名義の取引口座において従前と同様に取引を行っていたこと、③金融機関の担当者は、E名義の取引口座に係る取引の説明をする際、Aに対してではなく専らEに対して説明をしており、Aは取引の説明に口を出すことがほとんどなく、また、Aが入院した後は、上記担当者はEに対してのみ取引の説明をしていたことが認められることからすると、Eは、本件E名義預金等に係る取引について、いずれも自らの判断に基づき主体的に行っていたということができるのであり、本件E名義預金等を自ら管理及び運用していたということができる。
○ 一般に、財産の帰属の判定において、財産の管理及び運用を誰がしていたかということは重要な一要素となり得るものではあるけれども、夫婦間においては、妻が夫の財産について管理及び運用をすることがさほど不自然であるということはできないから、これを殊更重視することはできず、EがA名義でAに帰属する預金の管理及び運用もしていたことを併せ考慮すると、Eが本件E名義預金等の管理及び運用をしていたということが、本件E名義預金等がAではなくEに帰属するものであったことを示す決定的な要素であるということはできない。
○ 本件E名義預金等の原資はいずれもAが出捐したものであることについては当事者間に争いがないところ、AとEの年齢差も考慮すると、AはEの生活について金銭的な面で心配を有していたものの、その心配は、主として自分が死んだ後のことについてのものであったということができるのであって、Aが、自分の死んだ後にEが金銭的な面で不自由をしないように、本件遺言書の作成とは別に、自己に帰属する財産をE名義にしておこうと考えたとしても、あながち不自然とはいい難い。
○ そうすると、実際に生前贈与をした土地建物の持分については贈与契約書を作成し、Eが小石川税務署長に対して同贈与によって納付すべき贈与税はない旨の申告書を提出していたのと異なり、E名義預金等についてはそのような手続を何ら採っていないことも考慮すると、Aがその原資に係る財産をEに対して生前贈与したものと認めることはできないというべきである。
生前贈与された後に受贈者が当該財産を管理、運用することは当然ですが、そのような状況であったとしても、そのことのみを以ってして、生前贈与が成立している訳ではありません。
名義預金と認定されないためには、贈与契約書の作成、預金間の資金移動、各人毎に銀行印を分ける、贈与後の管理運用(書き換え時の筆跡等もチェックされる)等、生前贈与を適法に成立させる必要があります。
また、名義預金はスポットで受注した相続税申告の際に問題となるだけでなく、顧問先の社長が実は多額の名義預金を形成してしまっているにも関わらず、税理士がその事実を知らないこともあり得ます。
そういう意味では法人税の申告の際等に、相続税対策としての「適正な」生前贈与の方法を伝えていくことも重要と考えます。
特に、平成27年1月1日以降においては、20歳以上の直系卑属に対する生前贈与は相当額であってもかなり活用できる状況になっています。
名義預金は毎年の税務調査でも問題となりやすい項目ですので、生前から関与しているならば、その入口から出口までを一環してアドバイスしていくことが重要なのです。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。