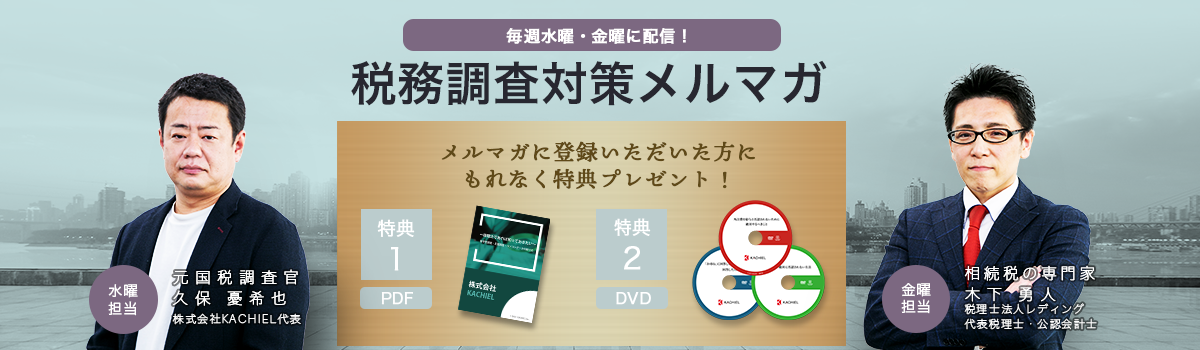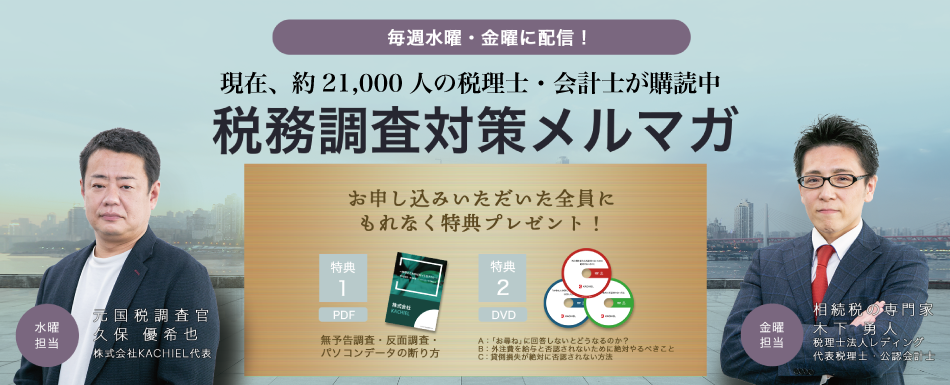役員退職給金の過大額
こんにちは。日本中央税理士法人の見田村元宣です。
さて、今回は「役員退職給金の過大額」です。
役員退職金を支給する場合、その金額が過大かどうかという判断を迫られることがあります。
そして、この過大額とは法人税法施行令第70条第2項に「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、
その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、
その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額」と定められています。
しかし、「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの」の抽出はなかなか難しく、
民間の各種データはあるものの、これを盲目的に採用することはできないのが実情です。
以前にもご紹介しましたが、TKCのデータを採用した複数の否認事例もあるのが現実です。
そうなると、代表取締役の功績倍率も3倍までに抑えておくことが無難な考え方にはなりますが、これは絶対的なルールではなく、その枠で常に考えることは保守的すぎると言えます。
そこで、参考になる判決をご紹介します(大分地裁、平成21年2月26日)。
この判決では、創業者(死亡退職)の功績倍率3.5倍が認められ、
役員退職金の適正額が1億9,425万円とされました(これを超える部分は否認された)。
なお、これは創業者であることも考慮されたものとなっています。
また、この判決では「平均功績倍率2.3を超える部分に相当する役員退職給与額については不相当に高額な部分になる
という被告の主張にも相応の根拠がないとはいえない」としながらも、功績倍率3.5を認めたことにポイントがあります。
以下、判決文の中から重要部分を抜粋します(一部、改訂)。
○原告(納税者)と比較法人の業績を比較すると、売上金額こそ概ね倍半基準の範囲内だが、
申告所得金額、総資産価額及び純資産価額のいずれの点でも原告が大きく上回るなど、原告は同業種・類似規模の法人に比して
経営内容が良好であるところ、平均功績倍率は、原告より全般に業績の劣る比較法人の平均値にすぎない。
○本件のように比較法人数が少ないと、法人抽出の範囲・方法により法人数がわずかに異なるだけで平均値は容易に変動してしまう。
実際に、前記のとおり、処分行政庁では比較法人中の2法人のみを算定基礎としたことにより平均功績倍率が3.094となったほか、
国税不服審判所長による裁決では福岡県の法人からも抽出して被告とは一部構成を異にする6法人を
算定基礎としたことにより平均功績倍率が1.6となっている。また、当該業界における功績倍率の平均値を
より客観的に求める観点からすれば、原告を加えて平均値を計算することも考えられるが、
この場合、被告主張の比較法人に原告を加えるだけで2.3から2.7へ増加することになる。
また、被告が採用した比較法人5社の功績倍率は、高いものから4.00、2.81、2.19、1.45、0.91となっているところ、1.45、0.91と低額に過ぎる一部の法人が存在することで
平均値が不相当に引き下げられているし、また、これらは平均功績倍率である2.3の周辺に集中しているわけではなく、相応のばらつきを見せている。
○このような功績倍率の分布状況から考えても、平均功績倍率である2.3を超えれば、直ちに不相当に高額であるとするには疑問の余地がある。
○さらに、後記のように創業者として多大な功労のあった乙のような創業者の功労等、報酬額に相当の影響を及ぼすと考えられる事情は平均値算出過程で基本的に考慮されていない。
○このような事情を考慮すれば、少なくとも本件においては、比較法人の平均功績倍率が役員退職給与の相当額を判断する際の重要な資料になるとしても、
平均功績倍率を用いて算出される金額をもって直ちに相当・不相当の基準とするのは相当ではなく(なお、前記のとおり、処分行政庁も、原告の採用した
功績倍率が平均功績倍率を上回ったからといって、直ちに不相当に高額であるとは判断していない。)
比較法人の平均功績倍率に加え、その功績倍率の分布状況、平均値算出過程では十分考慮されないが役員退職給与額に相当の影響を
及ぼし得る原告や乙の事情をも考慮して不相当に高額な部分の有無及び金額を判断するのが相当である。
○このように解することは、比較法人の功績倍率の分布状況も同業種・類似規模の法人の支給状況の要素と考えられるうえ、
退職給与として相当な額の判断基準として、業務に従事した期間、退職の事情のほか、上記法人の支給状況等を考慮するように定め、
これらの列挙事項以外の事情を考慮することについても否定するものではない、法36条及び法施行令72条の趣旨に反するものではない。
○これを本件について検討するに、乙は、個人で運送業を始めた数年後に原告を設立した創業者であり、
昭和43年から平成14年の死亡退職に至るまでの間、代表取締役を務めて原告における営業活動を一手に引き受けていたこと
原告の利益率は同業種・類似規模の法人の中では突出して高く(別紙別表1によれば、
売上総利益率は12比較法人の平均の2倍以上である。)、乙の退職前10年くらいの間は原告に毎年平均して4500万円程度の所得を計上させるなど、原告を収益性の高い法人に発展させたこと、
平成13年ころから大口取引先との取引終了により原告の売上高は減少し、平成14年3月期には経常利益で赤字を計上するものの、
リストラや不動産業による安定収入の確保等により翌期には経常利益等を回復させたことが認められ、以上によれば、創業者として好業績の法人である原告を維持発展させた乙の功績は極めて大きいものといえるところ、
このような事情は、創業者であること等を比較法人の抽出条件とはしない平均功績倍率の算出過程では考慮されるものではないが、役員退職給与額に相当の影響を及ぼし得る事情と考えられる。
○処分行政庁においては、2法人のみを比較法人として平均功績倍率を3.094と算出し、
原告の採用していた功績倍率3.5を近似値として相当としているところ、2法人を抽出する過程で、欠損が多額であった1法人及び功績倍率のあまりの低さから本来あるはずの退職給与が支給されていない
と思われる3法人を除外したことについては、上記のような原告と他の同業種・類似規模の法人との業績の差異及び乙の創業者としての功績を踏まえれば、その判断に相応の合理性があるものといえる。
○以上の点に加え、前記の諸事情も合わせ考慮すれば、3.5を超えない範囲の功績倍率による役員退職給与については、直ちに不相当と評価することはできないものというべきであり、
他に上記範囲の功績倍率による役員退職給与が不相当と評価すべき事情を認めることはできない。
○一方で、功績倍率のうち3.5を超える部分に係る役員退職給与については、比較法人の平均功績倍率2.3を大きく超えていること、比較法人の功績倍率の分布状況を見ても、5社中4社は功績倍率が3.0未満にとどまっており、
最高値である4.0はそれら4社と比べて突出して高いことなどからすると、原告及び乙に特有の上記事情を考慮してもなお、不相当に高額といわざるを得ない。
○(不相当に高額な部分について)以上によれば、乙の役員退職給与のうち相当であると認められる金額は、適正役員報酬月額150万円に勤続年数37年及び功績倍率3.5を乗じた1億9425万円であり、これを超える部分は不相当に高額な部分に当たる。
いかがでしょうか?
結果として、類似法人の選定はできませんが、功績倍率が3.0倍を超えていても当然ながら納税者の主張が認められる可能性はあるのです。
特に、今回のように、創業者であること、同業他社よりも利益率が高いこと等の個別事情がある場合はなおさらです。
優良会社の社長(特に、創業者)が退職する場合、役員退職金の額が相当額になることも少なくありませんので、そのような場合はこの判決の考え方を
覚えておいて頂ければと思います。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2014年2月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。