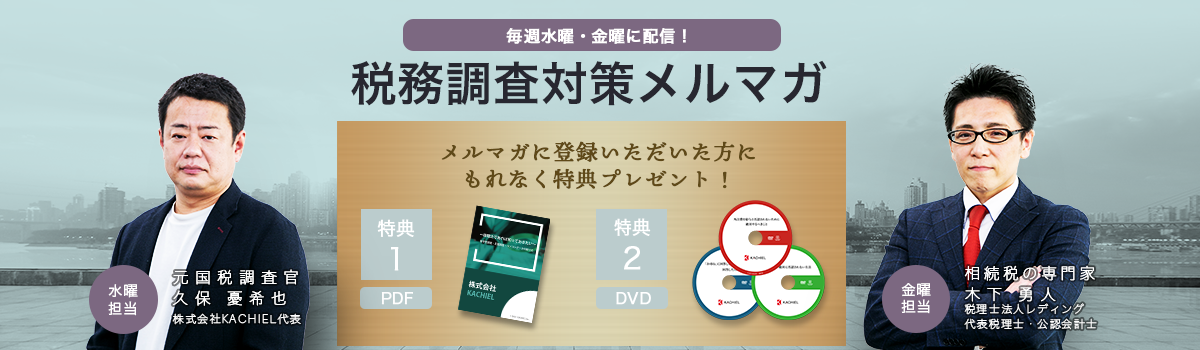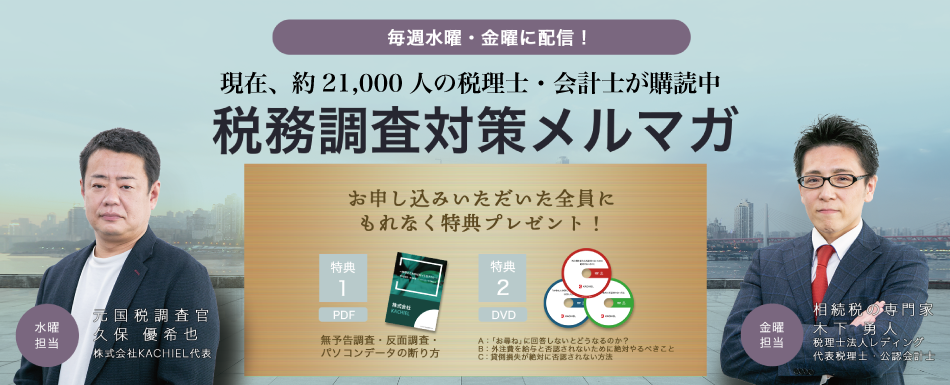役員退職金と分掌変更
こんにちは。日本中央税理士法人の見田村元宣です。
さて、今回は「役員退職金と分掌変更」です。
代表取締役が取締役会長や監査役に退き、役員退職金を支払ったが、実質的には退職していないということで否認されるケースがあります。
今回の事例(大阪高裁、平成18年10月25日、最高裁は上告不受理)も同様の状況で納税者敗訴となった事例です。
具体的な内容の前に分掌変更に関する基本通達をみてみましょう。
法人税基本津辰9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与
として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実
があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての
地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると
認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱う
ことができる。
(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を
有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を
占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2)取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な
地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号
《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を
除く。)になったこと。
(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその
法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が
激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注)本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が
未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
この裁判では代表取締役Aが取締役に、Aの父Bが取締役から監査役になり、
それぞれ4,000万円、1,560万円という退職金が支払われました。
そして、これが役員賞与として否認されたのですが、裁判の中で納税者は
「基本通達の(1)~(3)のいずれかに該当すれば、退職給与とすべき
である」と主張しました。
しかし、裁判所は
〇 これらの基準のいずれかを形式的に満たしても、他の事情も併せ勘案
すると役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職した
と同様の事情があるとはいえない場合にまで、退職給与として取り
扱ってもよいとは解されない
〇 退職後も担当する業務の実態が変わっていないこと、主要な取引先の
クレーム処理のような重要な業務を担当していたこと、常勤の取締役
として留まり新代表取締役と同額の報酬を得ていること、などにより
実質的に退職したと同様の事情があるときと認められない
と判断したのです。
ここまでは当然の内容ですが、本判決ではBが実質的に40%を超える
主要同族株主であることも論拠の「1つ」に挙げていますが、退職給与に
該当するかどうかは株主としての地位でなく、役員としての職務内容等から
判断すべき項目です。
実際、東京地裁(平成20年6月27日)や長崎地裁(平成21年3月10日)
では、主要株主という理由で分掌変更が実態として認められないとした
課税処分を取り消しています。
このうち、長崎地裁の判決文から一部を抜粋すると下記となります。
〇 丙は本件各事業年度を通じて原告の発行済株式総数のうち12%の株式を
有しており、法人税法施行令71条1項4号の要件のすべてを満たし
使用人兼務役員とされない役員に該当する
〇 本件通達によれば、そのような者が取締役から監査役になったときは、
取締役の退任に伴い支給された給与を退職給与として取り扱うことが
できる場合から除外されている。
〇 しかしながら、本件通達が退職給与として支給した給与を、法人税法上
の退職給与として取り扱うことができる場合として掲げている事実は、
その文言からも明らかなとおり、例示であって、結局は、役員としての
地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると
認められる場合には、その際に支給された給与を退職給与として損金に
算入することが認められるべきである。
〇 丙が取締役を退任し、監査役に就任したことによって、その役員としての
地位及び職務の内容が激変し、退任後も原告の経営上主要な地位を占めて
いるとは認められず、実質的に退職したと同様の事情にある
〇 被告(見田村注:原処分庁)は、同族会社の大株主が取締役から監査役に
なったとしても独立した機関であるという監査役の本来の機能は期待
できず、その地位又は職務の内容が激変したとは認め難いと主張するが、
一般的には、同族会社の大株主が監査役に就任したとしても監査の実効性
に疑問が生じることは理解できないわけではないが、平成17年法律
第87号による改正前の商法や商法特例法は、このような同族会社の
大株主であることを監査役の欠格事由としていなかったのであるから、
法は、このような大株主による監査についても一定の機能が果たされる
ことを期待し、可能であることを前提としていたというべきである
〇 そうであれば、法人税法施行令71条1項4号の要件のすべてを満たして
いる者については例外なく監査役の本来の機能が期待できないと解すこと
はできないから、被告の上記主張は採用することができない
〇 被告は取締役が監査役になっただけでは、役員の退職に該当しないとの
理解を前提に、そのような場合の使用人兼務役員に対する退職金は
退職給与に該当しないと主張する
〇 しかし、退職給与は、役務の対価として企業会計上は損金に算入される
べきものであるところ、取締役が監査役に就任し、その任務が激変した
場合であれば、その就任期間の役務に対して相当な退職金を支給した
場合として、役務の対価としての性格を有することから損金算入する
ことに弊害があるとはいえない
〇 退職給与は、取得した者については、所得税法上退職所得と取り扱われる
ところ、退職所得といえるためには、(1)退職すなわち勤務関係の終了と
いう事実によってはじめて給付されること、(2)従来の継続的な勤務に
対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、
(3)一時金として支払われることとの要件を備えることが必要である
(最高裁、昭和58年9月9日)とされている
〇 使用人兼務役員とされない役員が、取締役から監査役になり、任務が
激変していれば、実質的に勤務関係が終了しており(上記(1)の要件)、
その他の要件(上記(2)(3)の要件)も満たすから、これを退職所得と
みることに弊害があるとはいえない
〇 被告は、会社が解散して取締役が清算人に就任した場合、清算人も
役員であるが、その退職金は退職所得に該当するとして取り扱っており、
法人の役員である間は、原則として退職給与とならないとの被告の立場
に一貫性があるか疑問がある。
〇 使用人兼務役員とされない役員が取締役から監査役になった場合、
その任務が激変しているときには退職給与と認めるべきである
結果は一部認容ということで納税者の主張が認められた訳ですが、
このように分掌変更が問題になり、役員退職金が役員賞与として否認される
ケースは多々あります。
一般的な事例ではないかもしれませんが、学校法人の理事長が高等学校の校長
を退いた後、同法人の大学の学長に就任するも、退職給与として認められた
裁判例もあります(大阪地裁、平成20年2月29日)。
実態として退職していない場合はともかくとして、職務内容が激変して
いるような場合は、上記の判決などを提示してきちんと反論することが
大切です。
いつも記載していることですが、裁決や判決で納税者が勝ったということは税務調査の現場では更正されたということなのですから。
※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。
2013年10月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。