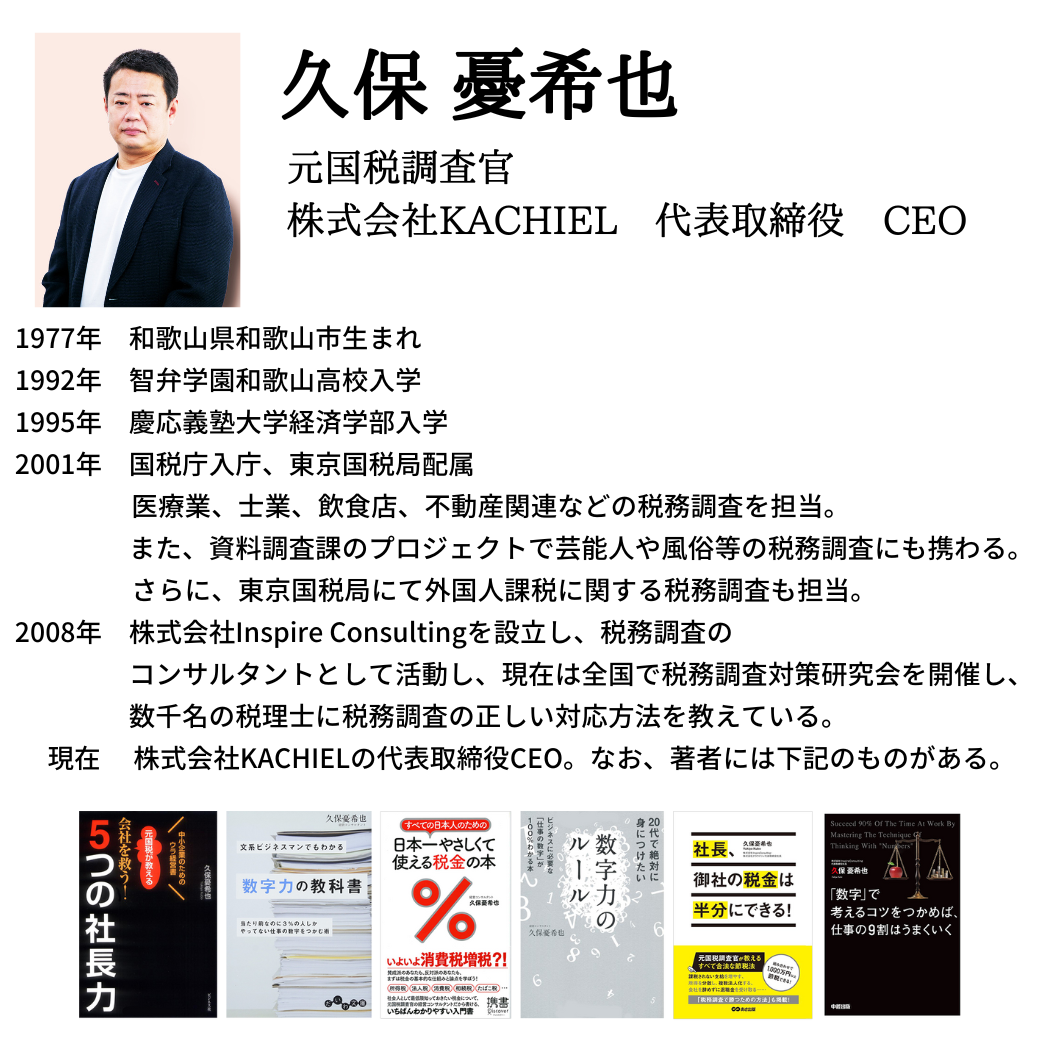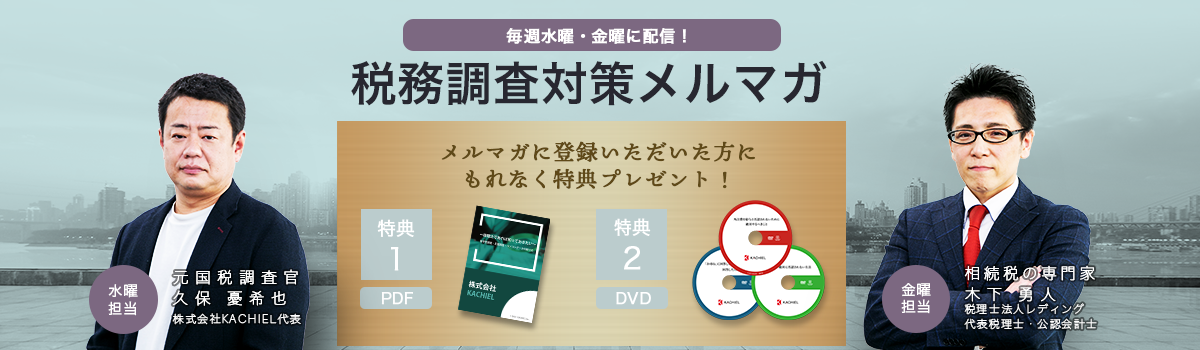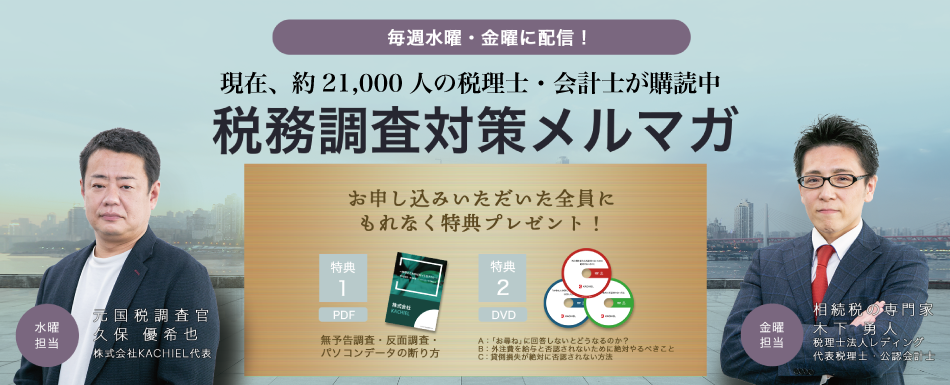扶養控除の対象範囲と判断に迷いやすい事例(前編)
※2024年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
今年も個人(所得税)の確定申告時期となりましたので、
水曜の本メルマガでは、今回から2月末までの配信について
個人の確定申告で判断に迷いやすい論点を解説します。
さて、今回は【扶養控除】の判定なのですが、この論点は
税務専門書でもほとんど取り上げられないにもかかわらず、
意外にも判断に迷うケースが多く、根本理解がされていない
領域なので、今回を含めて3回に分けて解説・配信します。
まず、「扶養親族」の要件を確認しておきますが、
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は
出国する場合はその死亡又は出国の時)の現況で、
次の4つの要件のすべてに当てはまる人を指します。
1 配偶者以外の【親族】
2 納税者と生計を一にしていること
3 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(令和元年分以前は38万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の
支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
上記1では【親族】とだけ規定していますが、親族とは
民法725条から「6親等内の血族及び3親等内の姻族」
を指します。具体的な範囲については下記をご覧ください。
厚生労働省サイト「親族の範囲について」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1027-8b.pdf
ここまでを前提として、今回はどこまでが
「扶養親族」に該当するのか、判断に迷いやすい事例を
取り上げます(来週は「生計を一」を論点にします)。
●再婚した妻に前夫との子(同居)がいる場合
このケースでは、夫と妻に婚姻関係があるものの、
その子は夫からすると実子ではなく、養子縁組でも
しない限り、親族に該当しないように思えてしまいます。
この場合の考え方は、妻は夫の配偶者であり、配偶者の
子であることから、夫からすると子は「1親等の姻族」
となり、扶養親族に該当することになります。
国税庁サイト「配偶者の子に係る扶養控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/67.htm
●亡くなった妻の父母(生計を一)がいる場合
こちらのケースは上記と逆の場合で、
妻と婚姻関係があったからこそ、夫からすると
妻の両親が「配偶者の直系尊属」だったわけですが、
その妻が亡くなった後も、妻の両親に送金するなど、
生計を一にしているケースです。
配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、
その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定される
わけではなく、生存しているうちに配偶者が婚姻関係を
終了させる意思表示をしていない限り、死亡した配偶者の
直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれますので、
扶養親族に該当することになります。
国税庁サイト「死亡した配偶者の父母に係る扶養控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/64.htm
●死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻を扶養控除
最後のケースとなりますが、年の途中で
夫が亡くなり、年末調整もしくは準確定申告で
妻を配偶者控除の対象とした場合、妻(子の母)が
生計を一にする子の扶養親族になるかです。
上記のとおり、扶養親族に該当するかは
「その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し
又は出国する場合はその死亡又は出国の時)の現況」
で判断しますので、夫側で配偶者控除の対象としていても
子側の年末調整もしくは確定申告において
妻(母)は扶養親族に該当することになります。
(所得税基本通達83~84ー1)。
ここまで「扶養親族に該当するか」を中心に
扶養控除の対象になるのかを考えてきました。
現実的によくありそうなケースであっても、
わりと判断が難しい場合もあったかと思います。
来週水曜の本メルマガでは、離婚して別居している
子供を扶養控除にできるのか、など扶養親族の
重要要件である「生計を一」について、
今回と同じようにケース別で解説していきます。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報