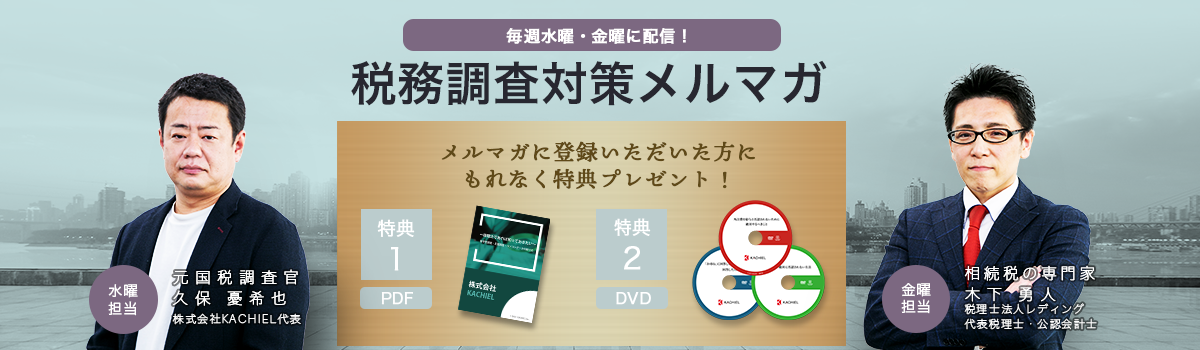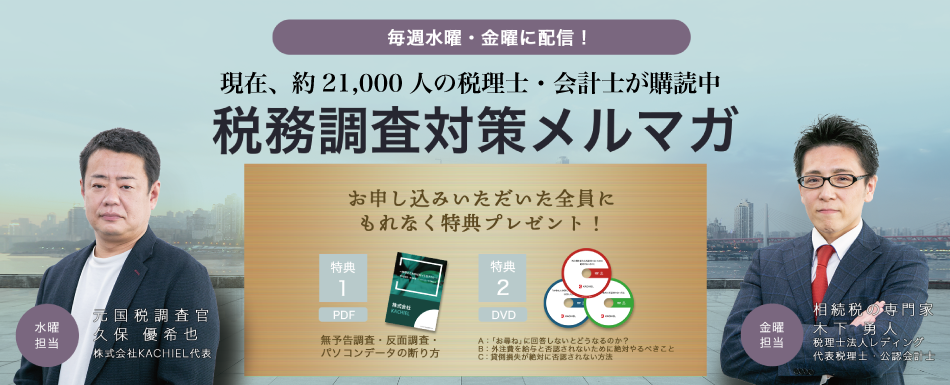抵当権の付されている不動産の評価の減額の是非
※2016年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「抵当権の付されている不動産の評価の減額の是非」ですが、
平成14年6月28日の裁決をご紹介します。
まず、本件に関する事実を時系列に整理します。
〇平成10年10月4日:相続開始
〇平成11年6月11日:相続税の申告
〇平成11年8月16日:A社は銀行取引停止処分を受けて倒産し、
代表者は行方不明。
〇平成11年8月16日:被相続人が借入れに際して担保提供していた
A社(B社の親会社)の倒産に連鎖して、B社も倒産した。
〇平成11年9月30日:土地建物について、■■銀行の申立てを受けて
競売開始決定がなされ、競売代金297,498,800円は、
競売に必要な経費を差し引き、同行からの借入金の返済に充当された。
ちなみに、A社は建売住宅の販売とマンションの賃貸を行っていた会社です。
この状況の下、被相続人が担保としてA社に提供していた土地の評価額が
争われた事案です。
なお、本件は更正の請求事案であり、当初申告において、
相続税評価額の合計額375,996,293円を相続財産として申告し、
この内訳は下記の通りです。
〇土地:374,381,928円
〇建物:1,614,365円
これに関する請求人の主張は下記の通りです。
〇次のとおり、本件土地建物については、本件相続開始日において担保権の
実行が確実であり、かつ、A社に対して求償権を行使しても
返還を受ける見込みがない状態であったと認められるから、本件土地建物の
価額から抵当権等により担保されている債務の額を控除すべきである。
・A社は、相続開始後特別な事象が起こっていないにもかかわらず、
約10か月後に倒産しており、これに伴って、A社に担保提供した土地、
建物の競売開始決定がなされ、競売された結果、回収金額はなかった。
・相続開始から倒産までの間に特別な事象が起こっていないのであれば、
相続開始時点においても、債務者が弁済不能の状態にあったと考える
のが社会通念に合っている。
・原処分庁は、異議決定書の中で、A社の決算書上の売上げ及び未処分利益が
堅調に推移しているから、弁済不能であったとは認められないとしているが、
同社と代表者が同一人であるB社は、従業員1人(実際にはゼロ)の
ペーパーカンパニーでA社と実質的に同一会社であり、平成5年3月期
から継続して債務超過の状態であったことを考えると、A社も、実質的には、
少なくとも平成5年3月期から継続して債務超過の状態であったと考えられる。
そして、国税不服審判所は下記と判断しました。
イ 請求人らの提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、
次の事実が認められる。
(イ)A社は、昭和50年に設立され、建売住宅の販売とマンションの賃貸を
行っていた。
(ロ)同社の法人税の確定申告書は、平成10年7月期まで提出されており、
平成10年7月期以前5事業年度の損益の状況は、次表のとおりである。
(単位 千円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
決 算 期| 売 上 | 粗利益 |販売管理費 |当期利益 |未処分利益
−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−+−−−−−−+−−−−−+−−−−−
6年7月期|2554844|390404|238296|27870|28900
7年7月期|2269996|316774|228769| 3424|32324
8年7月期|2633309|254516|209335| 792|30616
9年7月期|2792207|282896|204049| 3115|33732
10年7月期|2804572|288400|203555| 794|34527
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(ハ)同社の会計伝票の写し(平成10年8月分から平成11年4月分)に
よれば、平成10年8月以降の売上げは、次表のとおりである。
(単位 千円)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 年 月 |売上高| 年 月 |売上高| 年 月 |売上高
|−−−−−−−−−+−−−+−−−−−−−−−+−−−+−−−−−−−−+−−−
|平成10年 8月分|113|平成10年11月分|123|平成11年2月分| 99
|平成10年 9月分|202|平成10年12月分|342|平成11年3月分| 49
|平成10年10月分|335|平成11年 1月分|334|平成11年4月分| 46
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(ニ)A社の銀行借入れ及び返済の状況は、次のとおりである。
A 被相続人が担保提供した■■銀行からの借入金については、平成10年
8月まで元利金の返済を行っているが、それ以降は、平成11年7月までの間、
断続的に3回の利息支払のみを行っている(残債務額408,000千円)。
B ■■■銀行■■■支店(以下「■■■銀行」という。)からの借入れは、
短期借入金が平成10年6月、長期借入金が平成10年11月まで行われて
いる。また、返済は、短期分については平成10年8月以降平成11年1月
までの間に全債務額(278,000千円)が返済され、長期分2口に
ついては平成11年1月又は同年6月まで返済されている(残債務額
60,018千円)。
(ホ)A社は、本件相続開始日において、破産、和議、会社更生あるいは
強制執行等の手続開始を受けたり、又は事業閉鎖等の事実はない。
ロところで、抵当権等が付されている不動産の評価については、次のとおり
取り扱うのが相当である。
(イ)抵当権等が設定されている不動産については、次の理由から、
原則として、抵当権等が設定されていることを考慮しないで評価する。
A 抵当権等は、債務者又は物上保証人が債務の担保に供した不動産等を
担保提供者の使用収益に任せておきながら、債務不履行の場合には目的物の
価額から優先的に弁済を受けることを内容とする物権であり、債務の弁済に
より消滅し、また、目的物の処分についても何ら制限を加えるものではない
ので、抵当権等が設定されたからといって不動産の価値の低下はないこと。
B 債務者が自己の債務のために所有する不動産に抵当権等を設定させている
場合においては、債務は別途債務控除として相続財産の価額から控除される
ことになっており、他方、第三者が他人の債務の担保のため所有する不動産に
抵当権等を設定させている場合においては、抵当権等が実行されるか否かが
不確実であるほか、抵当権等が実行されたとしても債務者に求償することが
可能であるから、抵当権等を度外視した当該不動産の時価により評価するのが
相当であること。
(ロ)ただし、課税時期において債務者が弁済不能の状態にあるため、
抵当権等が実行されることが確実であり、かつ、債務者に求償しても弁済を
受ける見込みがない場合に限り、債務者の弁済不能と認められる部分の金額を
抵当権等が設定されている不動産の価額から控除して評価することとなる。
この場合において、債務者が弁済不能の状態にあるか否かは、一般に債務者が
破産、和議、会社更生若しくは強制執行等の手続開始を受け、又は事業閉鎖、
行方不明、刑の執行等により債務超過の状態が相当期間継続しながら、
他からの融資を受ける見込みもなく、再起の目途が立たないなどの事情により、
事実上債権の回収ができない状況にあることが客観的に認められるか否かで
判断されるべきである。
ハ 上記の事実から判断すると、次のとおりである。
(イ)A社の会計伝票の写しによれば、平成10年8月から平成11年1月
までの間通年ベースの売上げが計上されており、平成11年2月以降は
売上げが減少しているものの、倒産直前まで営業活動を行っていたことが
認められる。
(ロ)被相続人が担保提供した■■銀行からの借入れについては、平成10年
8月まで元利金の返済が行われ、その後も断続的にではあるが、平成11年
7月まで金利の返済を行っている。また、■■■銀行との間では、相続開始
以後も新たな融資及び相当額の借入返済が行われている。
(ハ)A社は、申告書に添付された決算書上、平成10年7月期まで
債務超過とはなっていない。
(ニ)以上のことからすれば、A社は、本件相続開始日前後を通じて営業活動
及び金融取引を行っていること、また、債務超過の状態が相当期間継続して
いたとも認めることができないことからすると、本件相続開始日において、
■■銀行のA社に対する債権が事実上回収できない状況にあることが客観的に
認められるとはいえず、A社が弁済不能の状態であったとは認めることが
できないから、本件土地建物の価額から根抵当権により担保されている
債務の額を控除することはできない。
ニ なお、請求人らは、相続開始から倒産までの約10か月の間に特別な
事象が発生していないのであるから、本件相続開始日においても弁済不能
であったと考えるのが社会通念に沿っていると主張するが、当審判所の調査
その他本件に関する全資料をもってしても、平成10年から平成11年に
かけての約10か月の間、建売住宅販売及びマンション賃貸の業種について、
同様の経営状態を維持しているのが一般的であると推認すべき事情を認めるに
足りる証拠もなく、上記ハのとおり、A社において、事実上、債権の回収が
不可能な状態にあることが客観的に認められるとはいえないから、請求人らの
主張は採用できない。
さらに、請求人らは、B社とA社が実質的に同一会社であることを考えると、
両社は実質的に相当期間債務超過であったと主張するが、両社は法律上
別人格の法人であり、B社が債務超過であるから直ちにA社も債務超過である
と判断することはできないこと、また、仮にA社が債務超過であったとしても、
その事実のみをもって弁済不能とは判断できないから、請求人らの主張は
採用できない。
いかがでしょうか?
これだけの状況でありながら、評価減が認められなかったことは非常に
不合理と感じますが、結果は結果です。
ただし、この事案に関し、名古屋国税局にて資産税の審理事務などを担当
された税理士の神谷光春先生はその著書「判例・裁決例にみる土地評価の
実務」の中で「請求人がA社の倒産に至った状況を明らかにしていれば、
判断も異なっていたかもしれないと思われる事案である。」と解説されて
います。
いずれにせよ、同様の事案に当たった場合には、評価減を当初申告で採用
するのか?更正の請求で採用するのか?も含め、相続人とも相談し、
慎重な判断が求められる部分になります。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。