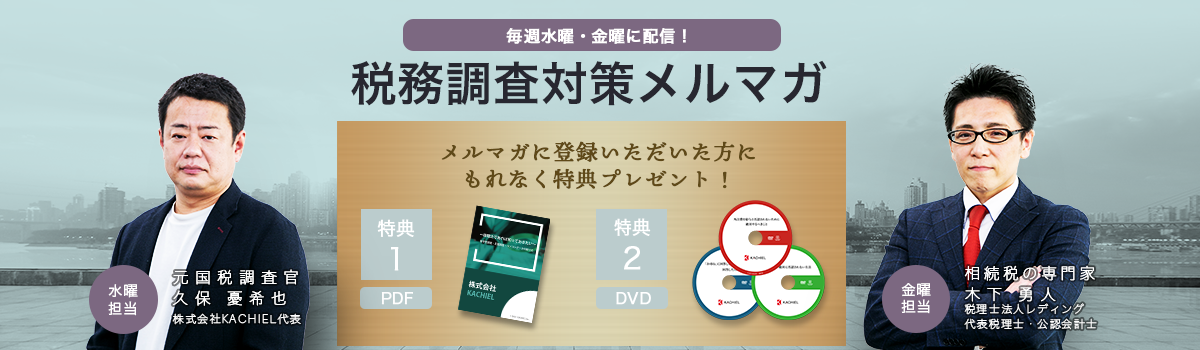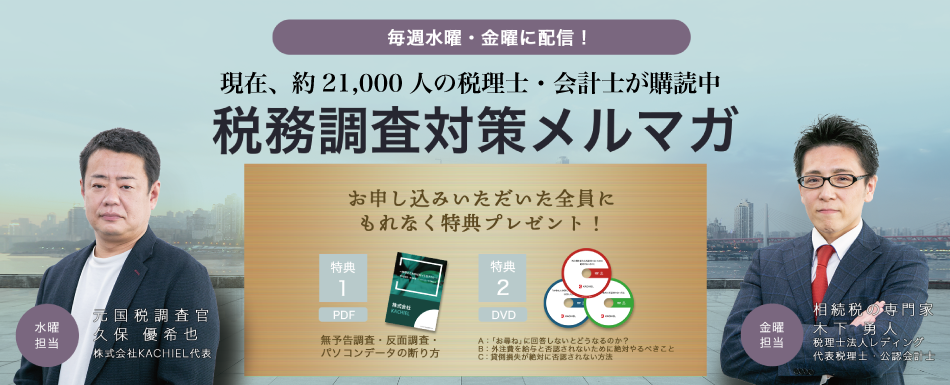死亡保険金と役員退職金の過大額
※2016年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「死亡保険金と役員退職金の過大額」ですが、
昭和63年9月30日の静岡地裁判決(平成元年1月23日、東京高裁にて
確定)をご紹介します。
この事案は
〇退職した役員が創業者であり、原告会社の事業の興隆に尽力したとの事情は、
原告会社が右役員の退職給与の額を類似法人の役員退職給与の支給額より、
著しく高額にするべき理由とはならないとされた事例
〇原告会社が役員の死亡に係る保険金収入と同額の金員を右死亡役員の
退職給与として支給していた場合、右保険金収入の存在は役員退職給与の
適正額の算定に当たり斟酌する必要がないとされた事例
です(その他の点は割愛)。
死亡保険金に限りませんが、不動産や有価証券の売却益など、
多額の収益が計上された場合、その金額に合わせ、役員退職金の支給額を
決めてしまう場合があります。
しかし、当然ですが、何かしらの原因により入金された金額と役員退職金の
適正額の間に相関関係はありません。
そのため、役員退職給与の過大額はそれ自体で判断されるべきものになります。
ちなみに、支給された役員退職給与は2億7,269万1,500円で、
課税庁は「最高功績倍率法」により、下記と適正額を計算しました。
1,400,000円×23年×4.1倍=132,020,000円
なお、類似法人5社の平均功績倍率は2.5でした(最低1.0、最高4.1)。
判決文のうち、主要な部分を抜粋します(Aが死亡した代表取締役)。
〇Aは、昭和27年頃、金属塗装業を営む〇〇塗装を創業、昭和34年頃
私財を投入してこれを法人組織にし、それ以来昭和57年7月18日死亡する
まで約23年間にわたり原告の代表取締役としてその存続発展に尽力して、
原告会社を浜松地域における業界随一の会社に興隆せしめたことが認め
られるが、Aの原告に対する功績は、その最終月額報酬に反映しているはず
であるから、右の事情は、被告による退職給与金適正額の算定に当たつて
考慮されているというべきであるし、また、別表1、2(割愛)の各法人に
おいてもそれぞれ右に類似し、あるいはそれに匹敵する事情がありうるわけ
であるから、右事情は、原告会社のAに対する退職給与の金額を類似法人の
役員退職給与の支給額より、著しく高額にするべき理由とはならない。
〇このように保険金収入と同額の金員を当該死亡役員の退職給与として
支給した場合であつても、利益金としての保険料収入と、損金としての
退職金支給とは、それぞれ別個に考えるべきものであるし、一般に会社が
役員を被保険者とする生命保険契約を締結するのは、永年勤続の後に退職
する役員に退職給与金を支給する必要を充足するためと、役員の死亡により
受けることがある経営上の損失を填補するためであるというべきであるから、
会社が取得した保険金中、当該役員の退職給与の適正額より多額であると
認められる部分は、役員の死亡により会社の受ける経営上の損失の填補の
ために会社に留保されるべきものである。
したがつて、被告が保険金の支払の有無をAに対する退職給与の適正額算定の
資料として特段の斟酌をしていないとしても、これをもつて、不当な算定
方法であるということはできない。
当社で運営している「税務相互相談会」でも、ある税理士の方から
同旨のご質問があったことからも分かる通り、顧問先のご遺族は
法人側で計上される収益の額から役員退職金の額を判断する可能性が
あります。
確かに、被保険者である役員の死亡により入金された金額ではあるので、
その感情が理解できない訳ではありません。
場合によって、税務上の過大額の論点は関係なく、その額が遺族の今後の
生活にとって必要な額であることもあり得ます。
この場合は過大額に関係なく、敢えて払い出す場合もあるでしょう。
しかし、法人側での過大額の判断はこれ自体でされるものとなりますので、
死亡保険金であったり、遺族にとっての必要保障額であったりすることは
過大額の判定には関係ないのです。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。