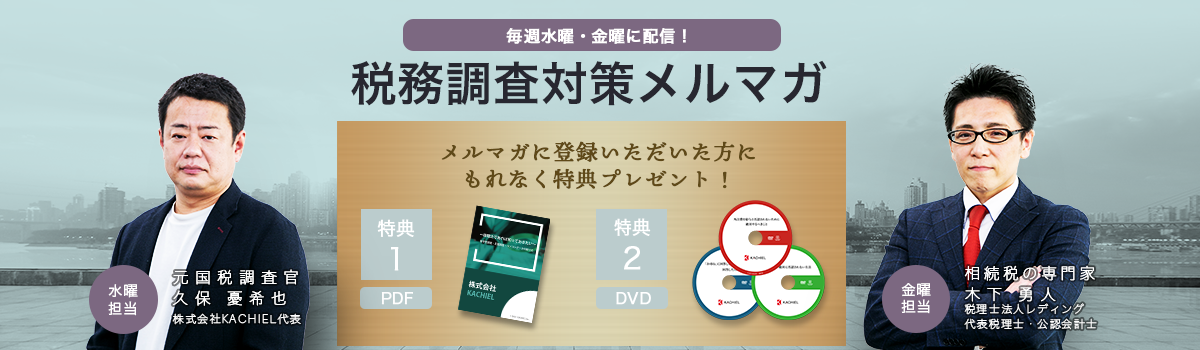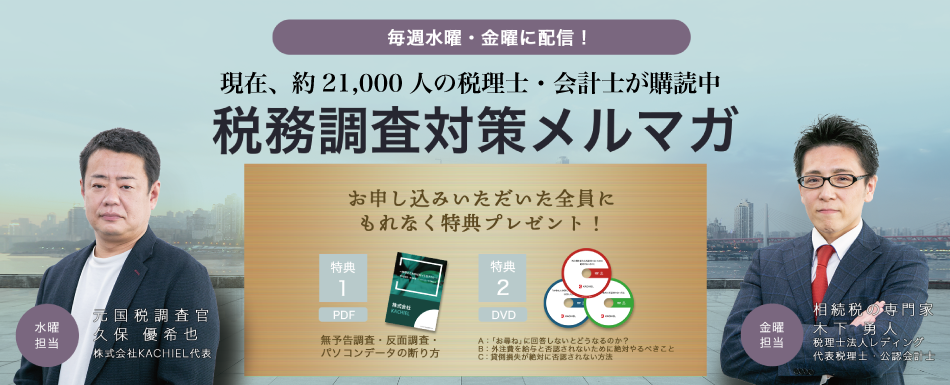生計一の定義とは?
今回は「生計一の定義とは?」です。
生計一かどうかによって様々な特例が使える場合、使えない場合が分かれますが、その線引きに関しては100%の明確な基準がある訳ではありません。
そこで、今回はその定義(線引き)を巡って争われた事例をご紹介します。まずは、「生計一」に関して記載されている通達です。
○所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
○法人税基本通達1-3-4(生計を一にすること)
令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する「生計を一にする」こととは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居していることを必要としない。
○国税通則法基本通達、第46条関係(生計を一にする)
9 この条第2項第2号の「生計を一にする」とは、納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居をともにしていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養しているときが含まれる。なお、同一家屋に起居していても、互いに独立し、日常生活の資を共通にしていない親族は、生計を一にするものではない。
「生計一」に関してはこれらの通達があるのみで、税法上の定義を明確に定めたものは無いのが現状なのです。
では、具体的な判決(東京高裁、平成16年6月9日)に移ります。ちなみに、この裁判は上告棄却、確定となり、納税者敗訴となったものです。
具体的には、弁護士が税理士(妻)に支払った報酬が必要経費になるかどうか?(生計一の親族に対するものか?)につき、争われたものです。
では、この判決文を細かくみてみましょう。
○ 法に規定する「生計を一にする」とは同一の家屋に起居している場合に限られるものではないが、この場合には明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これに該当するものと解される
→ 逆に言えば「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」ならば、別生計
以下、上記考え方の本件への当てはめ。
○ 夫と妻は自宅で同居し、食事も共にしており、食費、子供の学費、 旅行の費用等の家計はその都度話し合って、夫6:妻4の割合で負担
→ 「居住者と生計を一にする配偶者」に該当
○ 妻は夫と同居しているものの、住所地でB税理士事務所を経営し 夫とは別に仕事をし、独立して生計を維持する収入がある
○ 自宅は区分所有となっており、B税理士事務所部分は妻名義(ローン、水道光熱費、コンピューターのリース代等の経費は、妻の銀行口座から引落しにより支払われている)
○ 自宅の玄関とB税理士事務所の玄関とは全く別になっている
○ これらの事実は夫と妻の事業とが区分されていること、または、 妻の事業と家計とが区別されているレベルにすぎない
○ 消費生活における区分を述べるものではないから、生計一に該当する
○ 家計費を一定割合で負担しあうことは別生計であるとは言えず、むしろ逆に生計一という状況を裏付けるものである
特に、最後の部分の原文はこう書いてあります。
———————————————————————
家計費を一定の割合で負担している事実は、「生計を一にする」との要件の充足を否定する方向に働くものとはいえず、むしろ逆にこれを裏付けるものである。
———————————————————————
結果として、双方に収入があり、生活費を負担し合っていたとしても別生計にはならないということです。この判決から学ぶべきことは、生計一では適用されない規定を使おうとし、別生計の状況にしようとする場合は注意しなければならないということです。
こういう場合に「敢えて」生活費を一定割合で負担し合うことはむしろ逆行したことを行なっているのです。
いかがでしょうか?
当然ですが、実態として生計一である状況を別生計である状況に移行することは簡単なことではありません。もちろん、税制の規定を考えて損得はあるのですが、その運用には十分な注意をしなければならないのです。
(見田村 元宣)
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
2013年4月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。