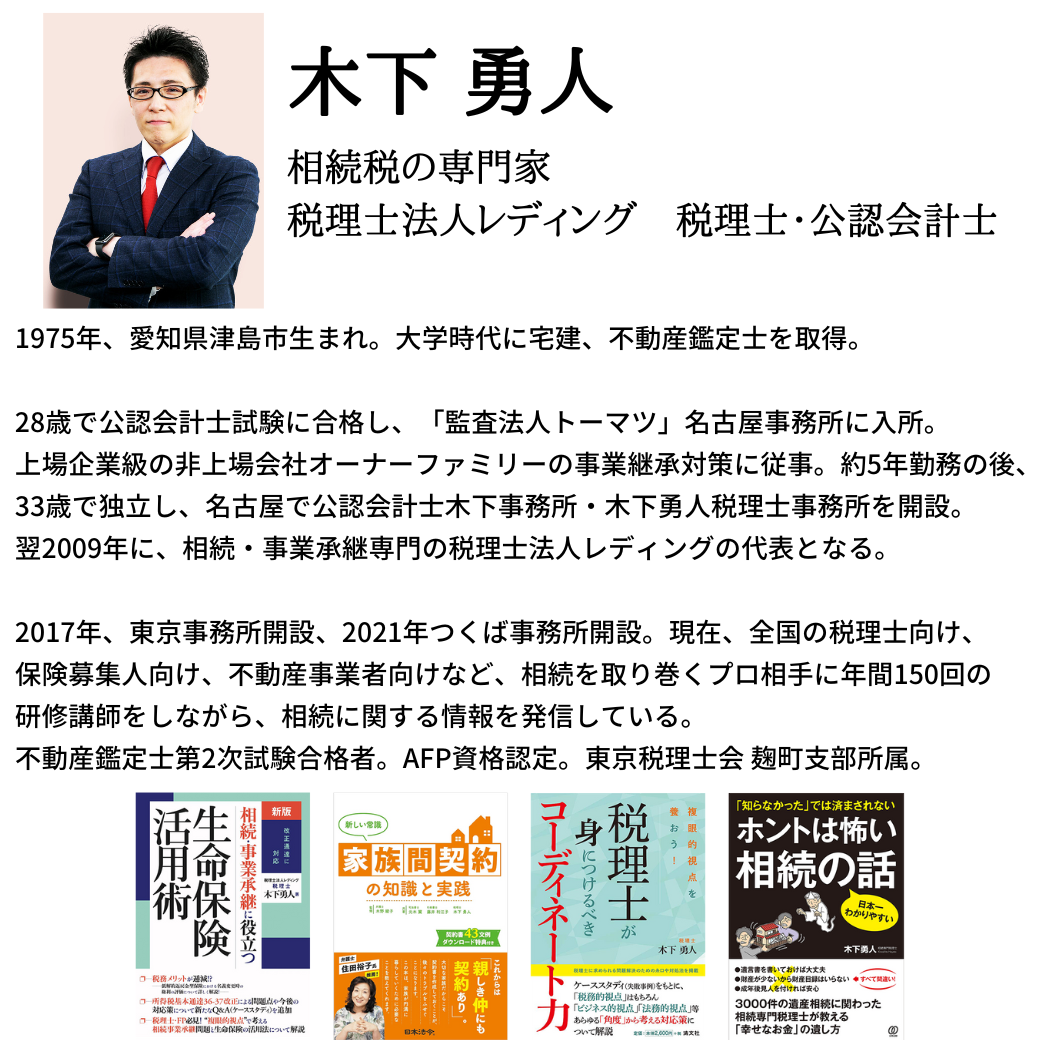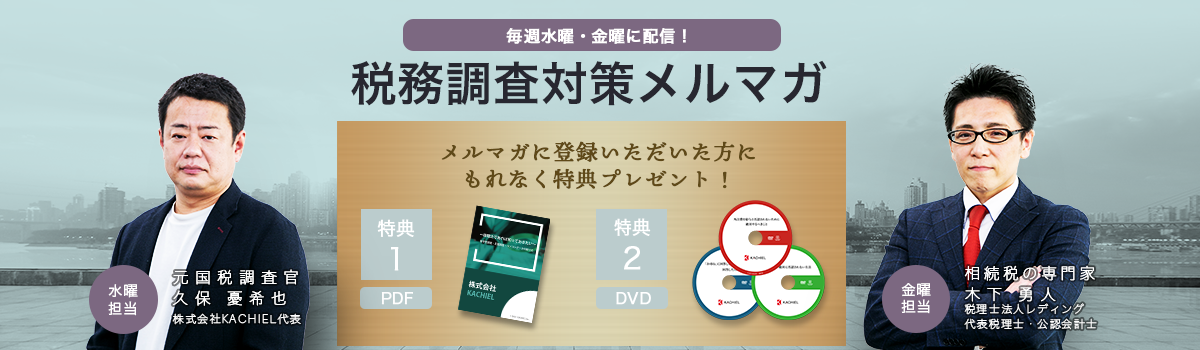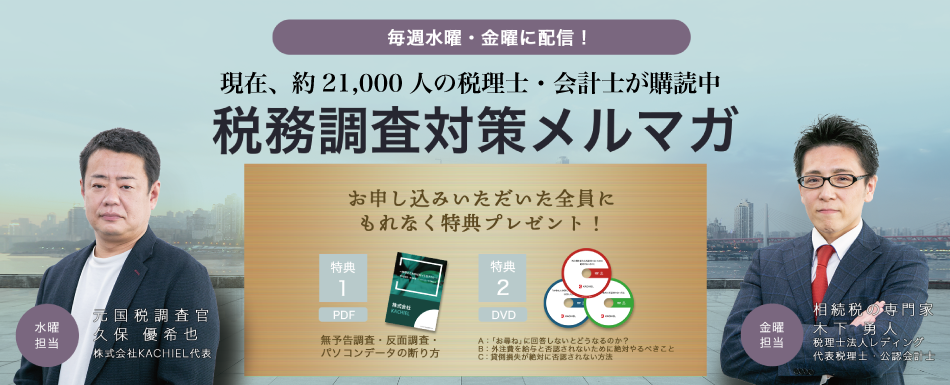相続時精算課税の具体的活用法(1)
※2024年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「相続時精算課税の具体的活用法(1)」です。
令和6年1月1日より
相続税に関する令和5年度税制改正が
施行されているのは周知の事実かと思います。
今回は改めて、
相続時精算課税の具体的活用方法を
検証したいと思います。
1.新設規定の積極活用
基礎控除(相法21の11の2(1)、措法70の3の2(1)(2))
が新設され、かつ、
相続時に基礎控除が加算対象から
除外される(相法21の15(1)、21の16(3))ことで、
相続時精算課税の積極活用が
想定されています。
具体的には・・・
110万円分の基礎控除を使って
生前贈与を検討する場合、
7年内贈与加算(相法19)の
加算対象者に該当する可能性が高い
相続人に対して相続時精算課税を
積極活用することが想定されます。
注意点としては・・・
特定贈与者が複数になる場合には
基礎控除が按分される(相法21の11の2(2)・相令5の2、
措法70の3の2(3)・措令40の5の2)ため、
110万円が全て加算対象とならない
状況も想定しなければならない、
ということになるかと思います。
2.高収益財産の贈与
被相続人が高収益財産を
そのまま保有している場合、
所得税負担をした手残りが
相続財産を構成することになります。
もちろん、手残りを相続発生
までに消費してしまえば
相続財産を構成することはありませんし、
加算されないことを考慮して生前贈与を
実行すれば、相続財産を構成することは
ありません。
かなりの収入を生む高収益財産、
例えば、賃貸しているテナント建物
であれば、土地を贈与しなければ
築年数にも依存しますが、
貸家減額を考慮し、基礎控除+特別控除を
大きくは上回らないのではないでしょうか。
また、仮に税額負担がある場合でも
贈与時期にも依存しますが、
賃貸テナント建物からの収入で
納税負担は耐えられる可能性が
高くなります。
また、令和5年度税制改正の新設規定
(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例:措法70の3の3)
により、贈与した建物に災害が発生した場合
には、相続時に再計算されることに
なりましたので、相続時精算課税の
使い勝手は向上したと言えます。
国税庁:令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(P3)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
よく一般の方から、
子へ現金贈与してから
収益物件購入させるのではなく
自分で物件購入してから
収益物件を贈与した方が
貸家(貸家建付地)となるため
有利ではないか、と質問されますが
購入してからすぐに贈与すれば
特段の事情がなければ
税務リスクが高くなると想定します。
また、建物贈与をする場合には
(1) 登録免許税(登記建物のみ)
(2) 不動産取得税
(3) 司法書士報酬
(4) 税理士報酬
などのイニシャルコストの案内を
忘れないことも必要となります。
次回も引き続き、
相続時精算課税の具体的活用法を
検証します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報