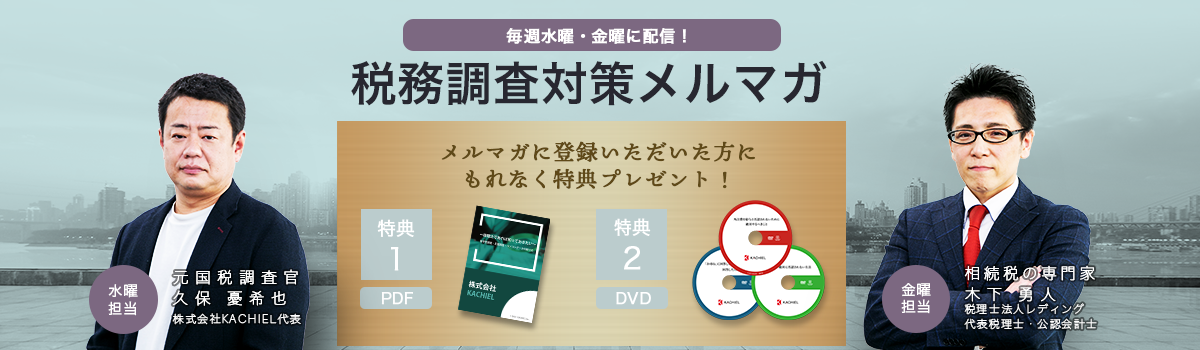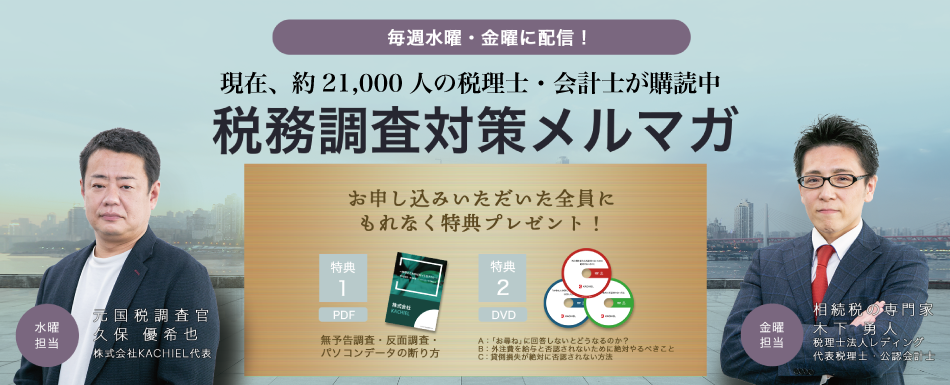社長の功績倍率3.0の根拠となった東京地裁判決
※2017年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「社長の功績倍率3.0の根拠となった東京地裁判決」ですが、
昭和55年5月26日の東京地裁判決を取り上げます。
なお、今日は少し長いですが、「社長の功績倍率3.0」の根拠となった
重要な判決ですので、是非、お読みください。
まず、前提条件を書きます。
〇 不動産の売買及び仲介幹旋等を業とする青色申告法人
〇 昭和47年8月25日に取締役O、M、Y、監査役Sが退職し、
退職金各1,500万円を未払金に計上
そして、国税の主張は下記です。
〇 同業事業規模類似法人は7法人で、その支給対象となつた役員は
13名であつて、その退職給与の支給状況及び功績倍率等は別表3
記載のとおりである(別表3は割愛)。
〇 これによれば、功績倍率の平均は1.9、最高は3.0であり、
右数値は本件更正当時の全上場1,603社の実態調査の結果から
算出される功績倍率の平均が社長3.0、専務2.4、常務2.2、
平取締役1.8、監査役1.6であるところからみて相当な基準と
いえるものである。
〇 原告に最も有利となる比較法人の功績倍率の最高値である3.0を
もつて相当とし、この倍率に基づき前記退職役員に対する退職給与の
相当額を算出すると別表4記載のとおり(割愛)、Oについては
60万円、M及びSについては各45万円、Yについては30万円、
合計180万円となる。
〇 従つて、各退職役員に支払われた退職金の合計額6,000万円のうち、
右180万円を超える5,820万円は過大な役員退職給与に当たる
というべきである。
この状況の下、東京地裁は下記と判断したのです。
〇 株式会社政経研究所が昭和47年6月20日現在で全上場会社
1,603社及び非上場会社101社を調査したところ、
何らかの形で役員退職給与金額の計算の基準を有しているものが
682社、そのうち右基準を明示したものが265社あつたが、
265社のうち167社が退任時の最終報酬月額を基礎として
退職金を算出する方式をとつており、さらに、そのうち154社が
最終報酬月額と在任期間の積に一定の数値を乗じて退職給与金額を
算出する方式をとつていることが認められるのであるから、
退職給与金額の損金算入の可否、すなわちその相当性の判断に
あたつて原告と同業種、類似規模の法人を抽出し、その功績倍率を
基準とすることは、前記法令の規定の趣旨に合致し合理的である
というべきである。
〇 被告所部係官が麹町、神田、下谷、京橋及び豊島の各税務署管内に
おいて、原告と同業種の不動産業(建売業、土地売買業)を営み、
役員退職の日を含む事業年度末の資本金が5,000万円以下の
法人について昭和46年11月から昭和47年12月までの間の
役員に対する退職給与の支給状況を調査したところ、役員に対して
退職給与の支給があつた法人は調査件数604法人のうち7法人で、
支給を受けた役員は13人であつて、その支給状況及び最終報酬月額、
勤続年数(6か月以上切上げ)、功績倍率(小数点第2位4捨5入)は
別表3記載のとおりであり、功績倍率の平均は1.9、最低は0.9、
最高は3.0であることが認められる。
〇 右認定の事実によれば、右比較法人の選定基準は不十分のきらいが
ないではない(事業規模が類似する法人を抽出するには資本金額
だけではなく総資産額、売上金額等も選定の基準とするのが望ましい。)
が、前掲乙第14号証によれば、抽出された7法人の期末総資産額
及び売上金額を原告のそれと比較すると前者は0.6倍(A社)
ないし10.8倍(G社)、後者は0.4倍(F社)ないし
11.8倍(G社)であつて、ばらつきが大きいものの、これらの
金額と功績倍率の大小との間には顕著な相関関係は見出し難いのであり、
従つて少くとも右比較法人の功績倍率の最高値を基準として
退職給与金額の相当性を判断する限りにおいては右選定基準の
不十分さの故に右判断の合理性が失われるものではない。
〇 そして、抽出された比較法人及び退職役員の数も資料の客観性を
担保するに足りるものであるから、右退職役員の功績倍率の
最高3・0を基準として原告の退職役員に対する退職給与の相当性を
判断することは合理的であるというべきである。
〇 ところで、原告は、原告のように設立直後の法人の場合は役員の
貢献の度合が未知であつて、それを報酬中に折り込むことは
不可能であるから退職金額の算定にあたつてはこの点を考慮
すべきであるし、また、退職役員の法人成立前の準備活動の結果
設立直後から大きな収益をあげたような場合は右準備活動も
退職金額算定の要素とすべきであるから、功績倍率の比較に
あたつては原告と同様に設立の日の属する事業年度において
多額の利益をあげた法人の功績倍率を採用すべき旨主張する。
〇 しかしながら、前記Oら退職役員の設立前の準備活動によつて
原告が設立直後から多額の利益をあげえたとの原告主張事実を
認めるべき的確な証拠は存在しないのみならず、一般に設立直後の
法人においては役員の貢献の度合を正確に報酬に反映させることが
できないため功績倍率が高くなるということを認めるに足る資料は
何もないし、また、退職役員の法人設立前の準備活動は、通常報酬
或いは賞与の金額を算定する要素とはなりえても退職給与金額算定の
要素とはならないのが通常であると解すべきであるから、前記法令の
規定の趣旨に照らし、功績倍率の比較にあたつては右準備活動の
有無を考慮する必要はないというべきである。従つて、原告の主張は
失当である。
〇 そこで、当事者間に争いのない各退職役員の最終報酬月額及び
勤続年数(いずれも1年に満たないが1年に切り上げる。)と
前記比較法人の功績倍率の最高3・0に基づき退職給与額を算出すると、
Oは60万円、M及びSは各45万円、Yは30万円となるから、
原告が役員退職給与として損金に計上した6,000万円のうち
右金額の合計である180万円を超える5,820万円は不相当に
高額な部分に当たるというべきである。
いかがでしょうか?
結果、この地裁判決が東京高裁(昭和56年11月18日)、
最高裁(昭和60年9月17日)でも支持された結果、
「社長の功績倍率は3.0」という話が定着したようです。
しかし、当然ながら、功績倍率で判断される場合においての
判断基準は平均功績倍率、最高功績倍率であって、
3.0が絶対的安全圏の倍率ではありません。
この判断は難しい部分ですが、社長の功績倍率は3.0程度を
基準としながらも、確定的には言えない旨を顧問先に伝えておくことが
重要なのです。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。