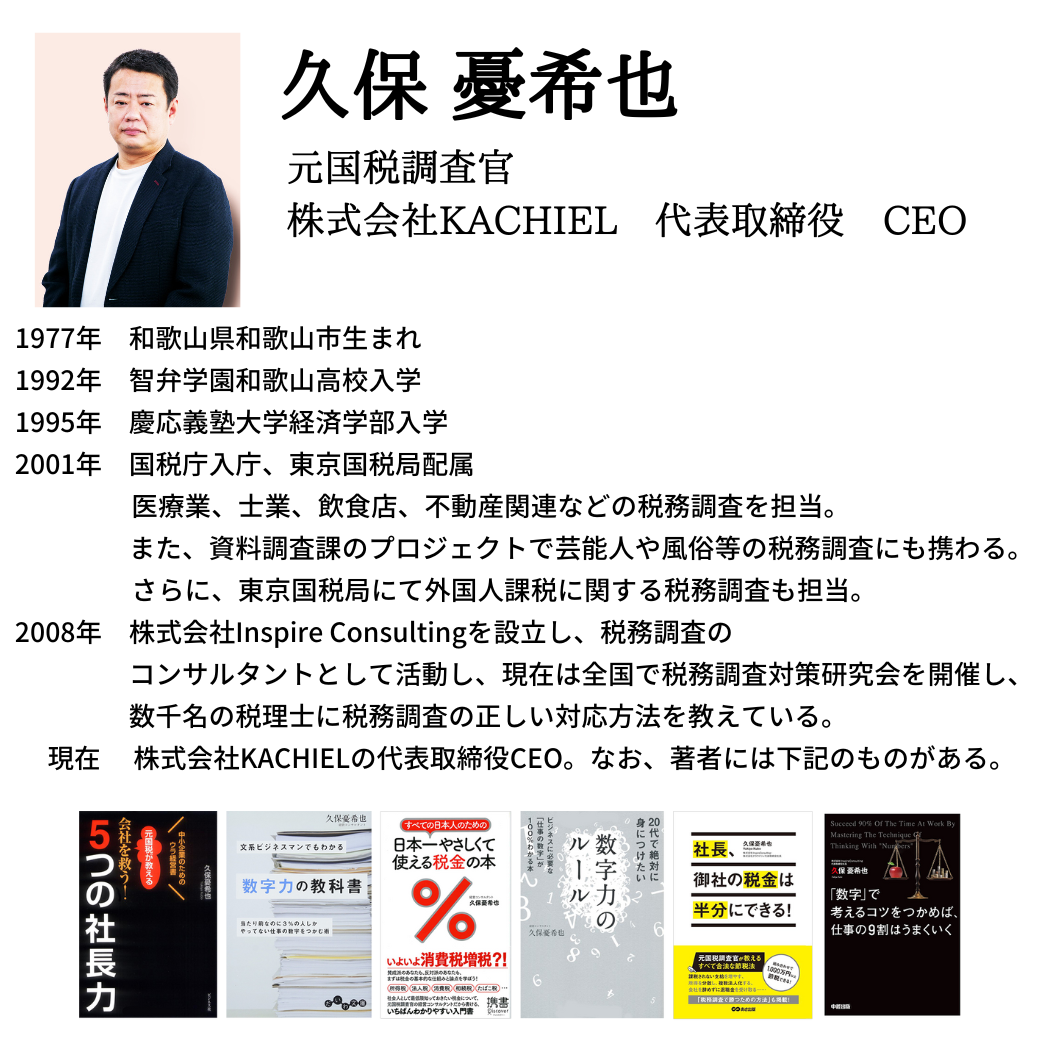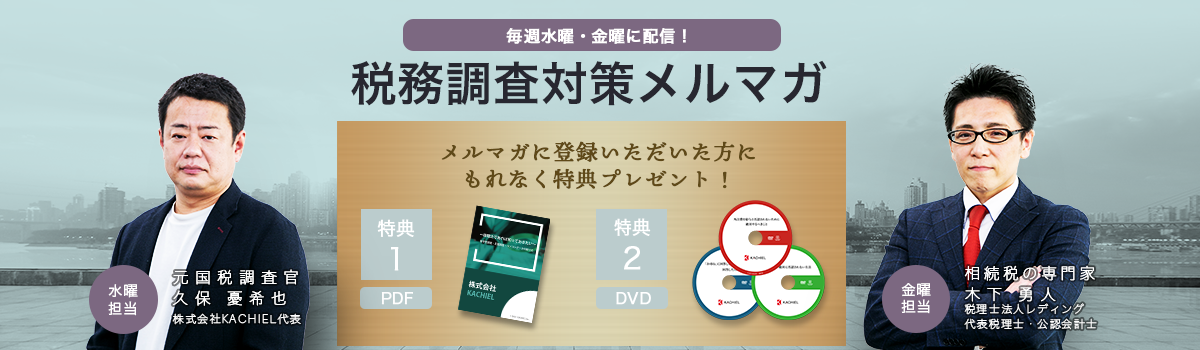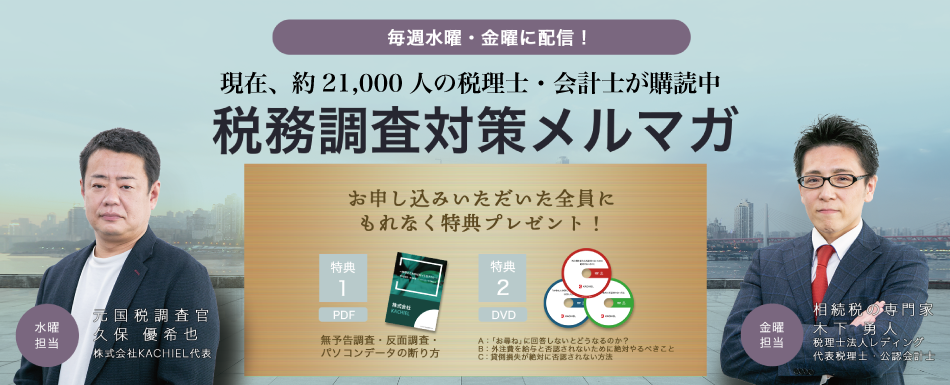税務代理とは何か?税務代理権限証書の提出義務との関係
※2024年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
先週水曜の本メルマガでは、今年4月から様式変更となる
税務代理権限証書とその意味合いについて解説しましたが、
今回はそもそも税務代理権限証書の提出義務は
どのような場合に・何を根拠に規定されているのか解説します。
まず、税理士における3つの独占業務のうち、
「税務代理」について税務調査の観点から考えてみましょう。
税理士法第2条第一号において、税務調査等における
税務代理を下記のように規定しています。
「当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは
処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは
陳述につき、代理し、又は代行すること」
併せて、この条文の通達を載せておきましょう。
税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)
2-4(代理代行)
法第2条第1項第1号に規定する「代理」とは、代理人の
権限内において依頼人のためにすることを示して同号に
規定する事項を行うことをいい、同号に規定する「代行」
には、事実の解明、陳述等の事実行為を含むものとする。
簡単に言えば、税務調査における税務代理(権限)とは
【納税者に代わって調査官に主張等ができること】
と理解すればいいでしょう。
ただし、税理士が税務代理権限を行使するためには、
税務代理権限証書の提出が義務となっています。
税理士法第30条(税務代理の権限の明示)
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で
定めるところにより、その権限を有することを
証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
さて、税理士の一般的な顧問契約を法的に分解すると、
税務代理=【委任】
税務書類の作成=「請負」
となるのですが、整理・解説された図示に関しては
下記のサイトを参照してください。
近畿税理士会の税理士法解説
第4章税理士の権利及び義務(第30条~第43条)
http://www.kinzei.or.jp/search/regulation/chapter_4_1.html
税務書類の作成を受託していない=顧問契約がなくても
税務調査の立会いはできるわけですが、その場合
調査立会いの前に税務代理権限証書を提出しなければ
ならないのも、上記で理解できるかと思います。
ここまでを全体的に(平易に)まとめると下記となります。
納税者が税理士に税務調査の立会いを【委任】する
⇒
税理士は納税者に代わって主張・陳述ができる
⇒
ただし、納税者が税理士に対して代理権を付与しているのか
税務署は外形的にはわからないので、税務代理権限証書を
提出する必要がある(提出を義務化している)
なお「委任」「代理」については民法の用語になりますので、
民法の規定を載せておきます。
民法第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示して
した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
今回は、税務代理と税務代理権限証書の提出義務について
解説しましたが、来週水曜の本メルマガでは
税務代理権限証書を提出しない税理士のリスクを取り上げます。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報