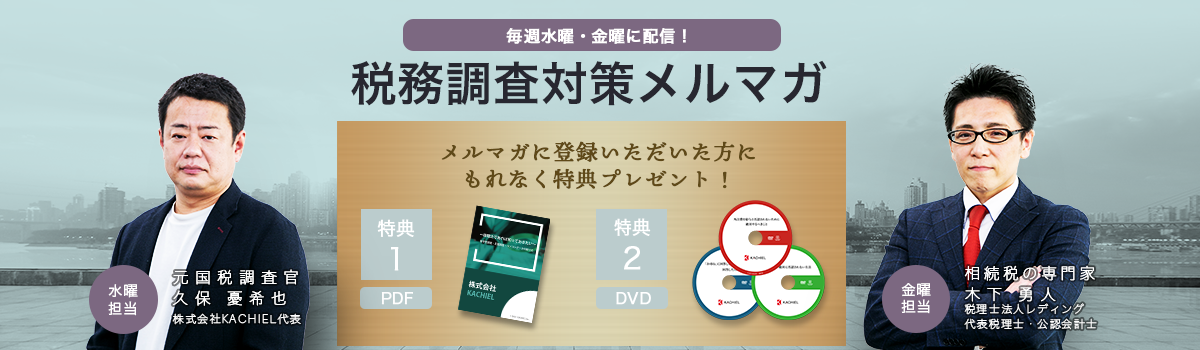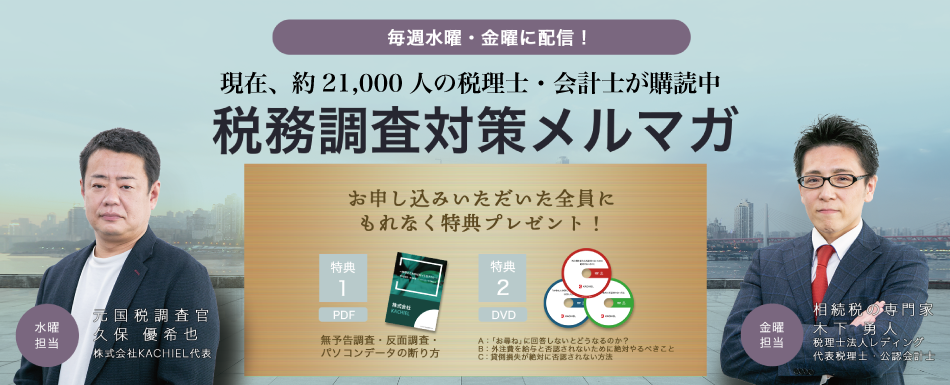財産の帰属が争われた事例
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
さて、今回は「財産の帰属が争われた事例」です。
相続税の税務調査において、相続人名義の財産はよく問題となる項目であり、
多くのケースで否認されています。
この場合、その財産がどう形成されたのか?、また、その財産の管理は
誰が行なっていたのか?などが論点となります。
今日の事例はこれが論点になり、地裁では納税者敗訴となりながらも
高裁では納税者勝訴となったものを取り上げます。
ちなみに、大阪高裁(平成13年3月1日)です。
まずは、事案の概要です。
○ 親族関係:祖母A、祖母Aの娘B、祖母Aの孫Cら
○ Bは昭和37年1月から昭和60年7月まで勤務しており、
死亡時の給与は約32万円、退職金は約1,161万円だった
○ 昭和58年1月にBは離婚し、元夫は養育費等717万円を送金
○ 昭和60年7月にBが他界し、当時未成年だったCらの後見人にAが選任
○ 平成4年1月にAが他界し、Aの財産をCらが相続
→ Cらは20歳と16歳
○ Aの収入はヤミ米販売、家賃収入
○ Cらはアルバイトをしており、平成2年10月から平成3年5月まで
約35万円
○ Cら名義の動産、不動産はA名義であると否認され、争いになった
そして、双方は下記と主張しました。
(納税者)
○ Cらが相続したB名義の財産は勤務中の給与、
別居中に夫から送金された生活費、離婚に伴う養育費等
○ 仮に、Aの預貯金等がBに移されたとしても、それは贈与されたもの
○ Cら名義の財産がBの財産を原資とするものでないとしても、
それはAがCらに贈与したものである
○ Aが管理していた財産はAの夫(Bの父)の相続に起因するもので、
Aが1/3、Bが2/3で相続したので、CらはBの財産を
相続したことになる
(課税庁)
○ Cら名義の財産が購入された当時、Cらは未成年であり、
その手続きに伴う印鑑がAの印鑑と同一、申込書もAの筆跡
○ Bの収入等から考えて、Bが数億円もの財産を形成したとは考えられず、
Bの死亡に伴う相続税の申告もされていない
○ Aが名義を使い分けていただけであり、BやCらに対する贈与の事実は
認められない
そして、裁判所(高裁)は下記と判断しました。
○ 相続財産である動産の帰属を確定するには、その管理の主体や内容も
重要な要素ではある
○ 被相続人が相続人の後見人であるなどの事情がある場合に、
Aが各動産についての取引行為を単独で行っていたこと、
Cらが未成年であったことという事実だけでは、各動産の帰属を定める
決め手とはならず、この帰属を判断するためには、その原資が誰に
帰属したかが重要な要素となる
○ Bの相続に関する相続税の申告がなされていないが、Bは少なくとも
2億円の動産を有していたので、申告&納税しなかったことは
遺憾であり、非難されるべき
○ この事実を併せ考えても、Bの相続財産を原資とするものが、
Aが管理していた財産に含まれるとみることができる
○ Aの財産が原資であることが明らかなものを除き、
残りの全てがAに帰属していたとまで認定することはできない
いかがでしょうか?
相続税の税務調査があった場合、相続人名義の財産が被相続人に
帰属すべきかどうかが問題になることはよくあります。
その場合、
○ その財産はどう形成されたのか?(原資)
○ その財産は誰がどう管理していたのか?
→ 預金であれば、印鑑の区別、口座開設や書換え書類の筆跡など
○ 贈与の事実は本当にあったのか?
→ 贈与を行なうならば、贈与ごとに書面を作成すべき
などが論点になります。
今回は一定の特殊事情があるとはいえ、財産の管理状態等が問題となり、
更正された結果、高裁までいって納税者勝訴となった事例です。
税務裁判になった場合は高裁まで争う意味を改めて感じた事例ですね。
それから、顧問税理士がついている場合でも法人のことだけに目がいき、
個人資産の管理状態まではチェック、提案ができていないことも
よくあります。
この結果、顧問先であるにも関わらず、社長等の相続税の申告を
しようとしたら、印鑑も親族で共通、管理も1人だけがしている、
贈与が成立していない名義預金もある、ということはよくあります。
少なくとも、上記の3つは確認し、提案しておくべきと思います。
そうでないと「先生、なぜ、教えてくれなかったのですか?」と
いうことにもなりかねません。
ご注意くださいね。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりません。
なお、2013年7月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。