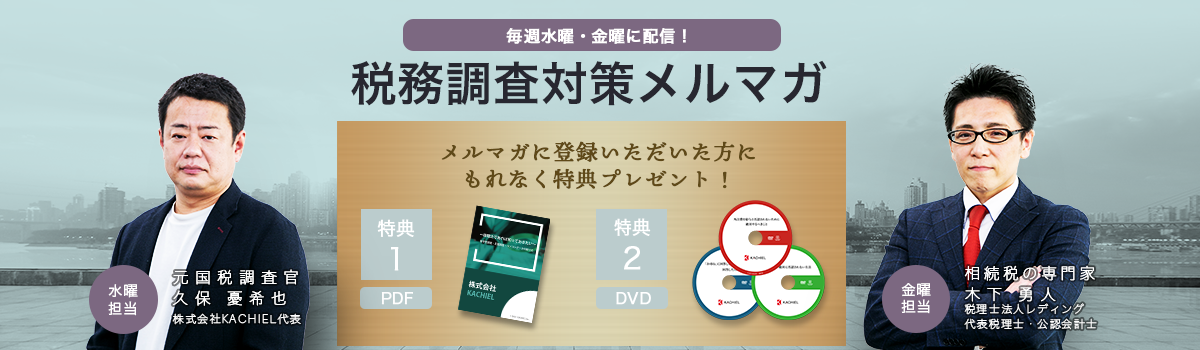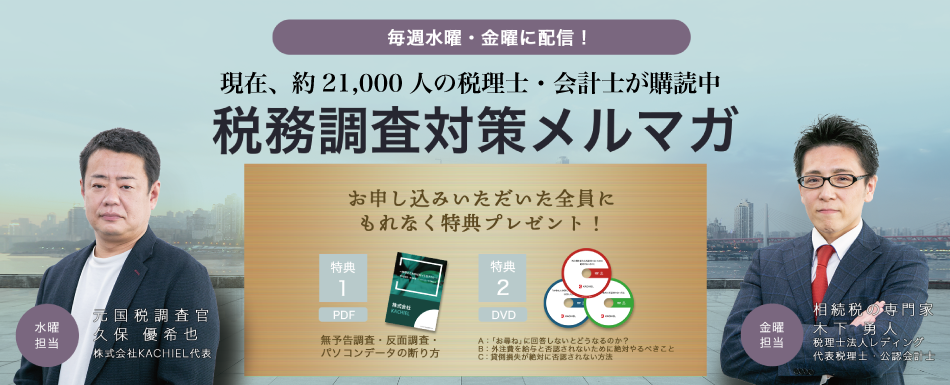財産評価基本通達と相続税法22条の時価
こんにちは。日本中央税理士法人の見田村元宣です。
さて、今回は「財産評価基本通達と相続税法22条の時価」ですが、
東京地裁(平成4年3月11日)を取り上げます。
まずは、この事案の前提条件から該当部分だけを抜き出します。
○ 被相続人A(95歳)は昭和62年12月19日に死亡
○ Aは同年10月9日に借入金8億円で賃貸マンションを購入し、賃貸
→ 購入価額は7億5,850万円
○ 支払利息:毎月約480万円、賃料収入:月額約166万円
○ 財産評価基本通達による本物件の評価額は約1億3,170万円
→ ここは原告、被告とも争いなし
○ Aの相続人は昭和63年4月から7月にかけ、7億7,400万円で
本物件を他に売却
○ 争点は相続税の計算をする上での本物件の評価額
では、結論の前に関係する条文等を確認しましょう。
○相続税法第22条(評価の原則)
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得
した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の
価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
○財産評価基本通達1(評価の原則)
財産の評価については、次による。(平3課評2-4外改正)
(1)評価単位
財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
(2)時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈
若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、
遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は
地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)に
おいて、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引
が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この
通達の定めによって評価した価額による。
(3)財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情
を考慮する。
○財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の
価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
結果としては、納税者の主張は認められなかったのですが、
東京地裁は下記の通り、判示しています。
○相続税法22条は、相続財産の価額は、特別に定める場合を除き、当該財産
の取得の時における時価によるべき旨を規定しており、右の時価とは相続開始
時における当該財産の客観的な交換価格をいうものと解するのが相当である。
○しかし、客観的な交換価格というものが必ずしも一義的に確定されるもの
ではないことから、課税実務上は、相続財産評価の一般的基準が評価通達に
よつて定められ、そこに定められた画一的な評価方式によつて相続財産を
評価することとされている。
○これは、相続財産の客観的な交換価格を個別に評価する方法をとると、
その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なつた評価価額が生じる
ことを避け難く、また課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理
が困難となるおそれがあること等からして、あらかじめ定められた評価方式
によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、
徴税費用の節減という見地からみても合理的であるという理由に基づくもの
と解される。
○そうすると、特に租税平等主義という観点からして、右通達に定められた
評価方式が合理的なものである限り、これが形式的にすべての納税者に適用
されることによつて租税負担の実質的な公平をも実現することができるもの
と解されるから、特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ右通達
に定める方式以外の方法によつてその評価を行うことは、たとえその方式に
よる評価額がそれ自体としては相続税法22条の定める時価として許容できる
範囲内のものであつたとしても、納税者間の実質的負担の公平を欠くことに
なり、許されないものというべきである。
○しかし、他方、右通達に定められた評価方式によるべきであるとする趣旨
が右のようなものであることからすれば、右の評価方式を画一的に適用する
という形式的な平等を貫くことによつて、かえつて実質的な租税負担の公平
を著しく害することが明らかな場合には、別の評価方式によることが許される
ものと解すべきであり、このことは、右通達において、「通達の定めによつて
評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示
を受けて評価する。」と定められていることからも明らかなものというべき
である。
○ すなわち、相続財産の評価に当たつては、特別の定めのある場合を除き、
評価通達に定める方式によるのが原則であるが、評価通達によらないことが
相当と認められるような特別の事情のある場合には、他の合理的な時価の
評価方式によることが許されるものと解するのが相当である。
○借入金による不動産の取得が転売利益を図ることをも目的として行われた
からといつて、このことによつて右不動産を評価通達によらず評価すること
が許される特別の事情の存在が肯定されなくなるものとすべき根拠は乏しい
ものといわなければならない。
○のみならず、前記認定のとおり、被相続人であるAはかねてから相続税
対策について関心を有していたところ、自己が病床にありしかも95歳
という高齢にありながら、自らの発意で8億円もの資金を毎月の利息負担
だけでも480万円になるという高利で借り入れて本件マンシヨンを購入し、
しかもこれを右1か月当たりの利息返済額の半額にも満たない月額166万
4000円でリクルートに賃貸することをしたのであり、これらの事実から
すれば、Aは、もともと本件マンシヨンが相続開始後間もなく他に売却される
ことを予定して、評価通達による不動産評価額が実勢価格よりも低廉である
ことを利用することによつて購入資金用の本件借入金と本件マンシヨンの
評価価額との差額分について課税価格を圧縮し相続税の負担の回避を図る
ため、本件マンシヨンの購入を行つたものであることが優に推認できるもの
というべきである。
いかがでしょうか?
借入金で賃貸不動産を購入して相続税対策をすることはよくありますが、
その方法が極端である場合、上記のような否認を受けてしまいます。
だから、そのタイミング、金額、経済合理性などを慎重に判断した上で、
相続税評価額を計算しなければならないのです。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2013年12月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。