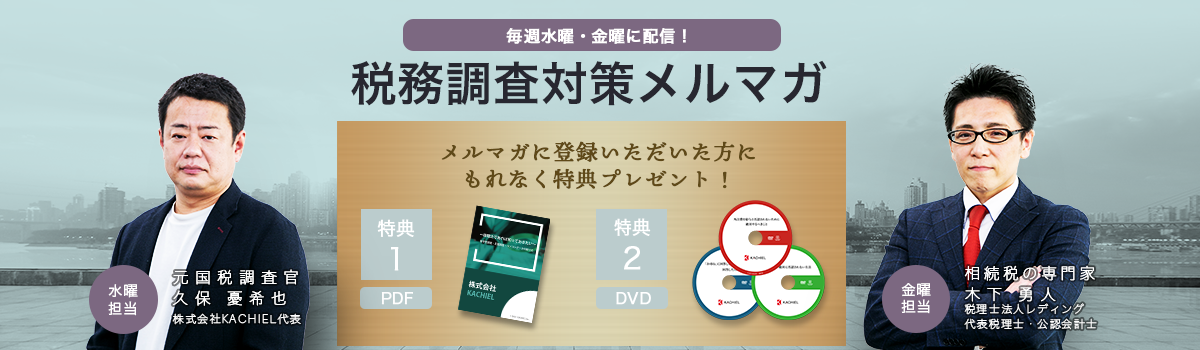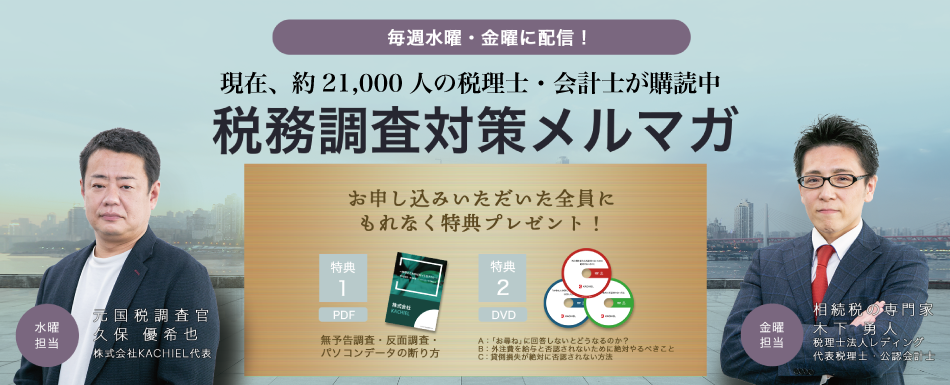父親が資金拠出の息子名義の車両は贈与か?
※2016年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は「父親が資金拠出の息子名義の車両は贈与か?」ですが、
平成27年9月1日の裁決をご紹介します。
この事案は父親が資金を拠出し、息子(請求人)名義で登録された車両につき、
贈与税の決定処分が取り消された事例です。
では、国税不服審判所の判断です。
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、
次の事実が認められる。
(イ)請求人は、G社の従業員である。
(ロ)父は、本件車両の前にもE車(以下「前車両」という。)を購入した
ことがあり、父が代金を支払い、父の名義で登録していたが、本件車両の
購入に当たって前車両を処分した。
(ハ)G社においては、その従業員がディーラーに紹介した客が車両を購入
すると、当該従業員が商品券等の特典を受け取ることができる紹介制度
(以下「本件紹介制度」という。)が設けられている。このこともあり、
父は、請求人がG社に就職して以来、父が経営する法人の社用車等を購入する
際には本件紹介制度を用いて請求人の紹介という形式を採ってきた。
(ニ)E車等の車両を製造販売するH社は、平成20年10月から同年末
までの間、同社が費用の一部を負担して、同社と取引関係を有する企業
(G社を含む。)及びその従業員向けのキャンペーン(以下「本件キャン
ペーン」という。)を実施することとし、ディーラーに対してこれを周知する
とともに、この機会を活用して積極的に営業活動を行うよう求めた。本件
キャンペーンの内容は、購入車両を上記対象企業及び従業員が本人名義で
登録することを条件として、車種に応じて(E車の場合は100,000円分)
購入車両の装備品等の割引をするとともに、購入者に20,000円分の
プリペイドカードを贈呈するというものである。
(ホ)本件車両についても本件キャンペーンが適用され、本件車両に装備
されるカーナビゲーションが100,000円分割引された。
(ヘ)本件車両の購入後の保険料及び自動車税は、全て父が負担していた。
(ト)請求人は、本件車両の購入以前から平成24年3月までは父の自宅に
住んでいたが、同年4月から平成25年12月までの間はdで生活をしていた。
その間、本件車両は父の自宅に保管されていた。
(チ)本件車両は、父の判断によって平成26年5月に売却され、売却代金は
父が受領した。そして、父は、同月中に新たにE車を購入し、自らの名義で
登録を行った。
ハ 判断
(イ)本件においては、本件車両の代金全額を父が負担しているのに自動車
検査証には請求人の名義で登録されており、相基通9−9に定める「他の者の
名義で新たに不動産、株式等を取得した場合」に該当するから、反証のない
限り、父から請求人への贈与として取り扱われる。そこで、反証の成否に
ついて検討する。
(ロ)本件車両の購入時点では、本件紹介制度(その内容に鑑み、客を紹介
したG社の従業員に与えられる商品券等の特典の額はせいぜい数万円相当の
ものであると推認される。)と本件キャンペーンが存したが、両者は車両の
登録名義人をG社の従業員(請求人)本人とするか否かという点で両立
しないので、いずれか一方しか利用できないものであったと認められる。
そして、本件車両を購入する場合の両者の効果を比較すると、本件紹介制度を
利用するより本件キャンペーンを利用する方が、少なくない額(装備品の
割引額及びプリペイドカードの合計額120,000円と本件紹介制度による
特典の差額相当額)を節約できることになる点で有利である。したがって、
本件車両の代金を負担する父としては、本件紹介制度ではなく本件キャン
ペーンの利用を選択するのが経済的に合理性のある行動であるといえる。
このことに加え、父は、本件キャンペーンの利用条件を満たすために、
請求人の名義を使用して本件車両を購入した(すなわち、あえて実質と一致
しない外観を作出した)ことは容易に推測されるところである。
(ハ)前車両は父が代金を支払い、父が登録名義人であったから、父が
自己所有物として購入したものであることは明らかであるが、当審判所の
調査によっても、請求人の家族について、本件車両の購入前後(すなわち
前車両の所有時と本件車両の所有時)で、その使用状況に変化を生じさせる
ような生活環境等の変動はなかった。そうすると、父所有の前車両が本件
車両に変更された際に、これを請求人に贈与する必要性は特別見当たらない
から、父が本件車両を請求人に贈与する動機はなかったと認められる。
(ニ)請求人及び父は、当審判所の調査に対し、本件車両を主に使用して
いたのは、父及び請求人の妹であるJであり、請求人は本件車両をほとんど
利用していなかったと認められる(請求人が平成24年4月以降dで生活
するようになっても本件車両が父の自宅で保管されていたことからすれば、
少なくともその頃からは請求人が日常的に本件車両を使用していなかった
ことは明らかである。)。そして、一般に、利用しない者に対して車両を
贈与するとは考え難いことに照らせば、このことは請求人への贈与の事実を
疑わせる事情といえる。
(ホ)請求人が父から本件車両の贈与を受けるつもりであったとすれば、
請求人が好みの車種や色等の希望を述べ、これが購入する車両の決定に
反映されるのが通常であるところ、当審判所の調査によっても、請求人が、
購入すべき車両の選定や購入手続等に関与した事実は認められない。
(ヘ)結局のところ、父は、自らの判断で購入すべき車両を選定して
本件車両の取得資金を出捐し、本件車両の維持・管理に必要な費用を全て
負担し、本件調査の開始後のこととはいえ自らの判断で本件車両を売却して
同売却代金を受領し、新たな車両を購入しており、これは正に所有者らしい
振る舞いであると評価できる。これに対して、請求人が本件車両の所有者
であったことを伺わせる事情は特に認められず、かえって、贈与があったと
すれば不自然ともいい得る事情の存在も認められる。
本件キャンペーンに関する事情に加え、上記の諸事情を総合すれば、本件に
おいては、上記イの推認(見田村注:相基通9−9)の前提となる経験則の
適用を妨げるための反証がされているというべきである。
したがって、請求人は本件車両の贈与を受けたとは認められない。
ニ 原処分庁の主張の当否
原処分庁は、本件車両はその代金全額を父が負担しているのに、請求人の
名義で登録されているから、相基通9−9により、原則として贈与として
取り扱うこととなり、本件においては本件通達(見田村注:「名義変更等が
行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(昭和
39年5月23日付直審(資)22、直資68国税庁長官通達。)の5の
要件を満たさず、これが適用されない旨主張する。
確かに本件は、相基通9−9に基づき、原則、贈与として取り扱うべきもの
である。しかしながら、本件通達は、相基通9−9の要件を満たしている
にもかかわらず課税庁の立場から贈与として取り扱わない場合を類型化した
ものにすぎず、相手方による反証はこれに限定されるものではないところ、
本件においては、本件車両の贈与の不存在について反証がされていると
いえるから、本件通達の5の要件を満たすか否かにかかわらず、上記結論は
左右されない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。
いかがでしょうか?
本件そのものは特殊な事例ではありますが、「名義借り」ということは
一般的にもよくある話です。
これが贈与とされた訳ですから、怖い話です・・・。
しかし、資金の拠出状況、その後の管理状況等を総合的に考えて判断すべき
ものですので、単なる「名義借り」につき、贈与と判断されることは
間違っています。
もし、名義借りについて贈与との指摘を受けた場合には、本裁決を提示し、
反論していきましょう。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。