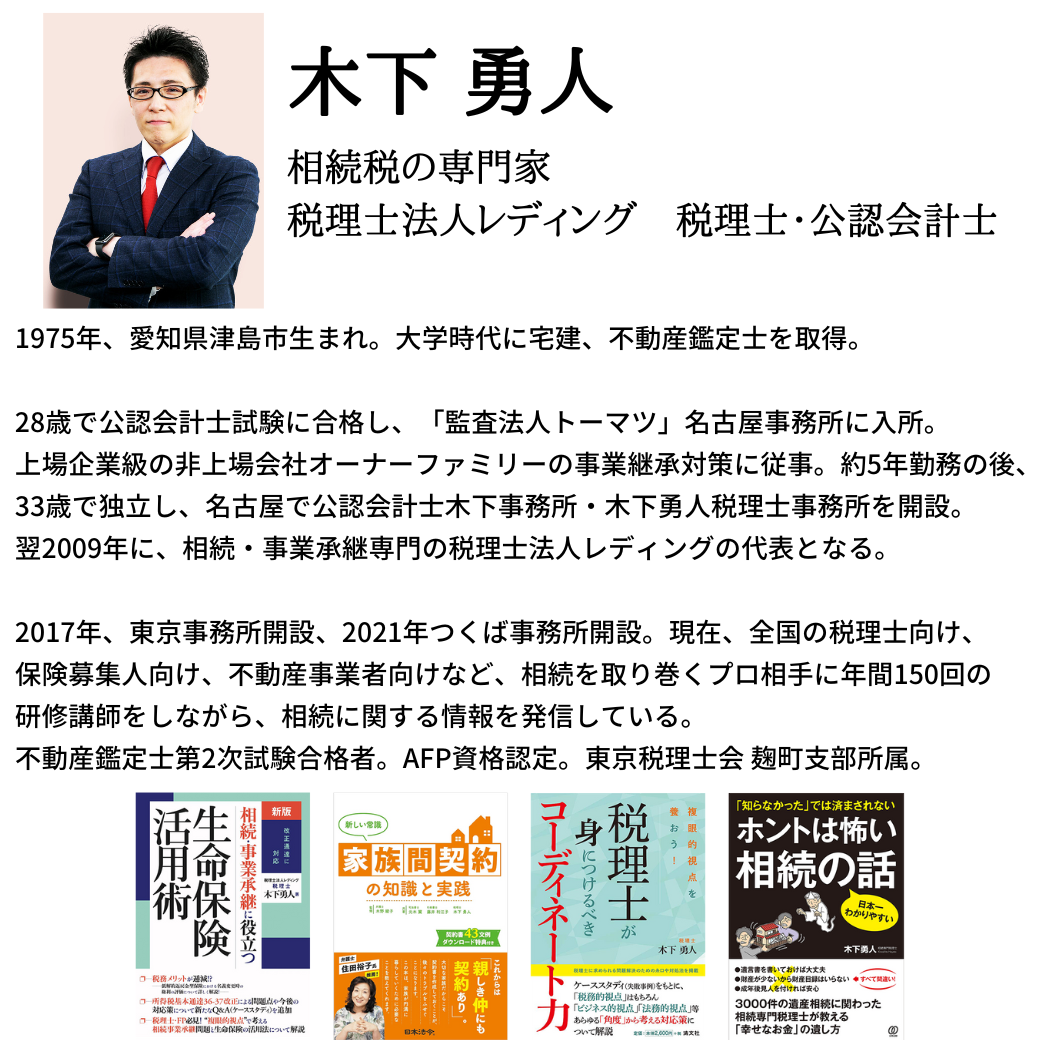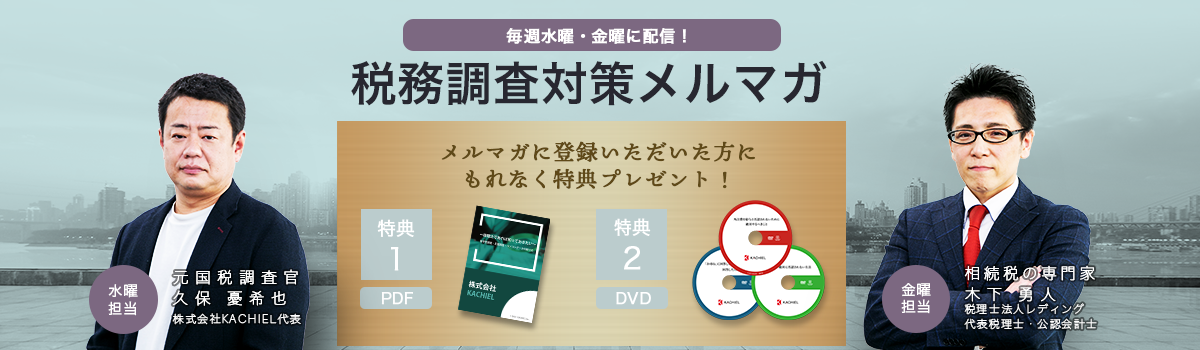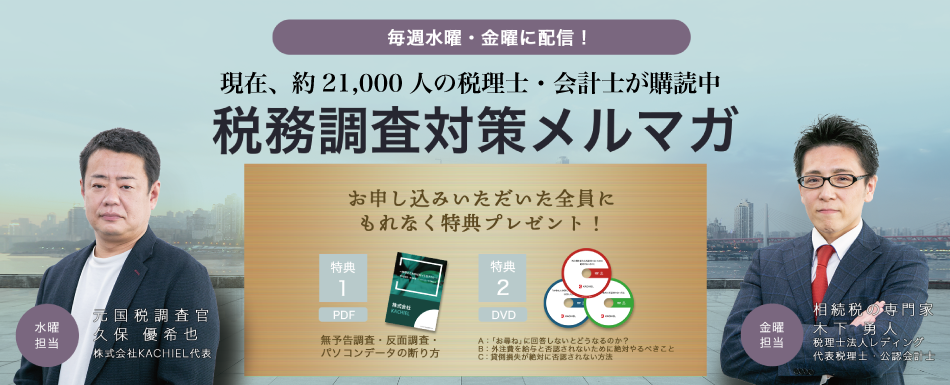相続時精算課税のリスク確認(1)
※2024年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「相続時精算課税のリスク確認(1)」です。
前回までの3回分は
「相続時精算課税の具体的活用法」を検証しました。
今回からは複数回に渡り
相続時精算課税のリスク確認を
していきたいと思います。
項目を列挙すると以下のとおりです。
1.選択後は暦年課税に戻れない
2.基礎控除を超える贈与は「期限内」申告が必要
3.小規模宅地等の特例は適用不可
4.相続税が発生することあり
5.物納不可
6.特定贈与者よりも受贈者が先に死亡する
それでは・・・
1つずつ、確認をしていきましょう。
1.選択後は暦年課税に戻れない
これはとても有名な話ですが、
相続時精算課税を選択して届出をすると
生涯継続して適用されることになります
(相法21の9(3)(6))。
令和6年1月1日以後の贈与につき
相続時精算課税でも基礎控除が新設され
かつ
特定贈与者の死亡時には当該基礎控除分は
精算しないことになりました
(相法21の15(1)、21の16(3))。
これまで何度もお伝えしてきましたが、
基礎控除(110万円)分の生前贈与であれば
相続時精算課税を積極活用するケースが
圧倒的に増加することが想定されます。
ただし、相続時精算課税では、
贈与時の相続税評価額をもって
相続時に精算するという特徴があることから
価格が下落局面にある財産は
相続時精算課税に向かないという
特徴があります(相法21の15(1))。
つまり、相続時には再評価を行わず、
贈与時の課税価格で加算することになります。
ただし、令和5年度税制改正により
土地建物に関する災害特例が新設され
この場合だけは、再評価されることに
なっています(措法70の3の3)。
ちなみに、贈与時の課税価格で加算する
理由は主に以下の3点だと言われています
(第一法規:コンメンタール相続税法)。
—
イ 相続税・贈与税はともに相続や贈与を契機とする財産の移転に着目して課税されるものである。
相続時精算課税制度では,相続時に相続税で精算することを前提としているとはいえ,
贈与時において既に受贈者は財産を取得しており,その後自己の責任と計算においてその財産を運用し,
そのすべての効用を享受している以上,贈与時以後における贈与財産の価値の変動結果は
すべて受贈者に帰属すべきものと考えられること
ロ 贈与税について累積課税方式を採用している諸外国においても,
贈与財産を相続時に再評価している例はまれであること
ハ 相続時までに贈与財産は形を変えており,インフレ調整等も決めがたいなど,
実務上の対応が複雑となること
—
仮に、相続時精算課税を選択後
自社の業績悪化により
自社株の相続税評価額が急激な下落局面に
入った場合では、相続時精算課税が
不利に働くことになるため、
相続時精算課税の選択を取りやめ
暦年課税に戻ることはできません。
令和5年度税制改正により、
相続時精算課税の使い勝手が増しましたが
価格が下落可能性のある財産を贈与する
場合には、相続時精算課税は向かない
というデメリットは
従前どおり変わりがありません。
そのような財産を贈与する局面を検討する
場合には、相続時精算課税の選択は
相当慎重に行うべきと考えます。
次回以降も、
相続時精算課税のリスク確認を解説していきます。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報