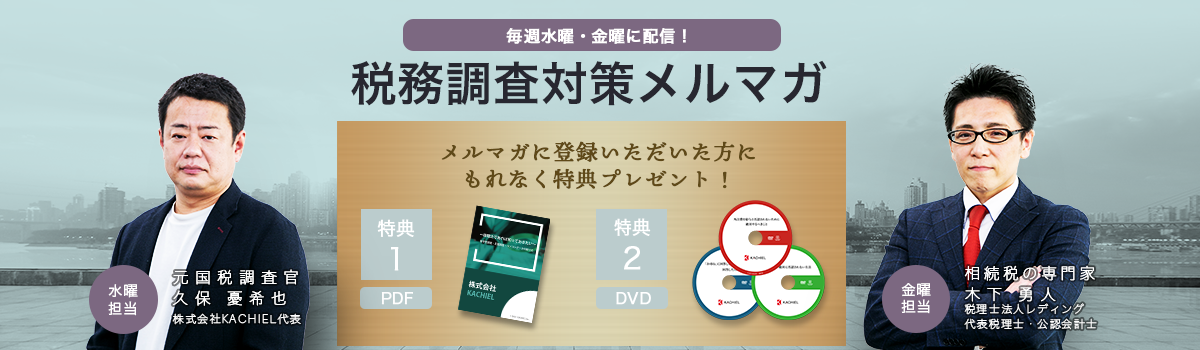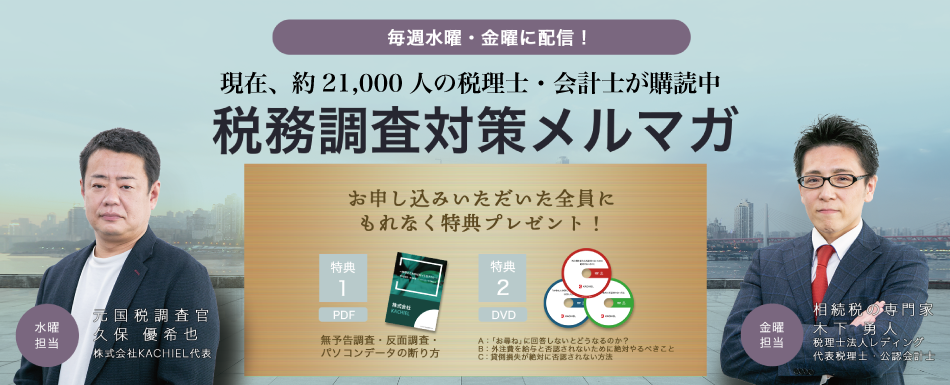貸倒損失の総論・全体像
※2020年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
これからしばらくの間、
「貸倒損失」についてシリーズで解説します。
実務上よく出てくる貸倒損失ですが、
特別損失に計上する
⇒
税務調査に選定されやすい
⇒
貸倒損失の計上基準が不明確
(実際には所得が計上された期に計上、
もしくは気付いた期に計上しているなど)
⇒
損金性を否認・期ズレ、さらには
5年以上前の貸倒損失で時効(否認)
など、論点が多い項目であり、かつ
多額になりやすいので注意が必要なのですが、
意外に深く考えられていない論点でもあります。
また、民法改正(時効など)の影響も含めて、
今回は「総論」ですが、次回以降に順次、
論点を細かく解説していきます。
まず、法人税法上貸倒損失を個別に定めた
法律規定はなく、第22条3項3号の
「当該事業年度の損失」に該当すれば
損金になるという考え方です。
この「損失」については、金銭債権が
社会通念上回収が不可能と評価できる事実が
必要(課税要件)になるわけですが、
その基準が曖昧であることから、実務上は
法人税法基本通達9ー6ー1~3が存在する、
という大きな枠組みで理解してください。
9-6-1:法律上の貸倒れ
9-6-2:事実上の貸倒れ
9-6-3:形式上の貸倒れ
一般的には、9-6-3から判断した
貸倒損失の計上が多いとは思いますが、
債権は法的に残っているものの、実質的に
回収できない(と顧問先が言う)場合は、
9-6-2の判断が必要なケースもあります。
貸倒損失の可否について税務調査では
事実認定によるところが大きいため、
督促・相手方の状況など、いかに客観的な
事実を残すのかも大事になってきます。
次回は、税務調査で
よくありがちな「債権時効は5年なので、
期ズレもしくは税務上の時効で損金に
ならない」という調査官の間違った指摘に
反論する方法を解説します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。