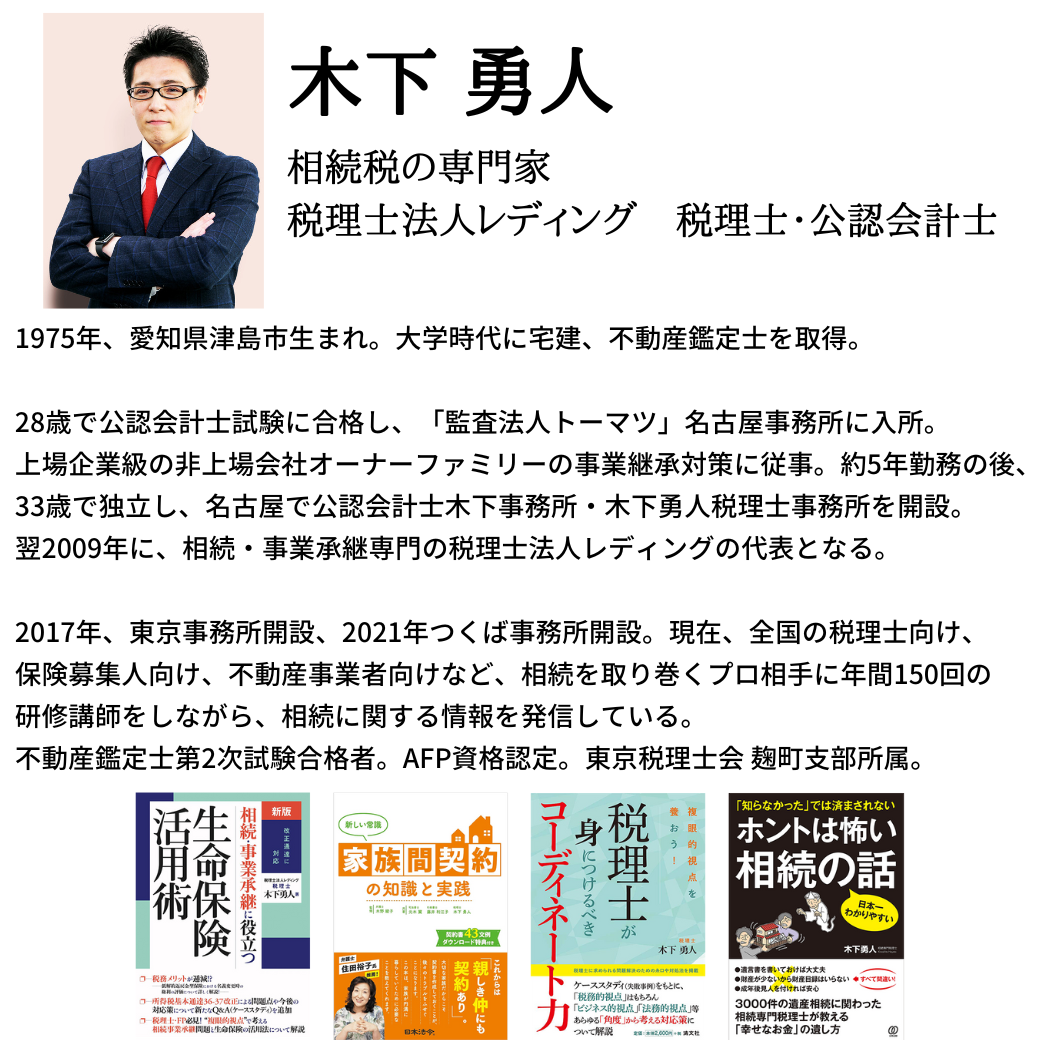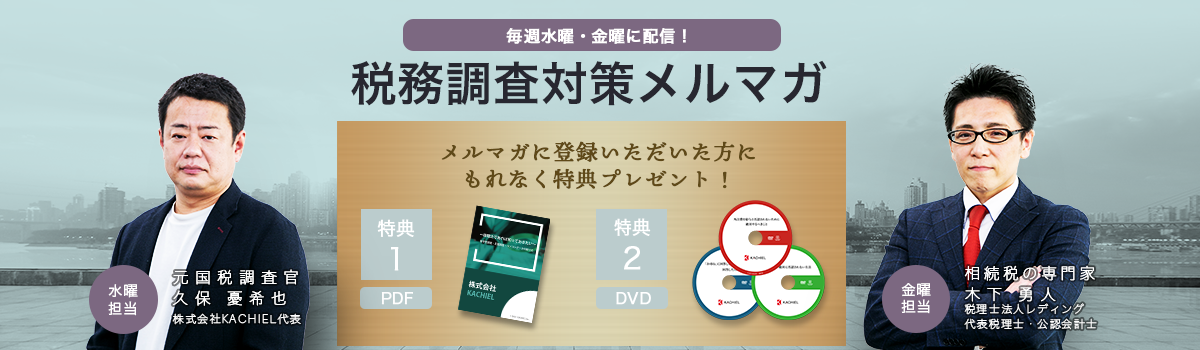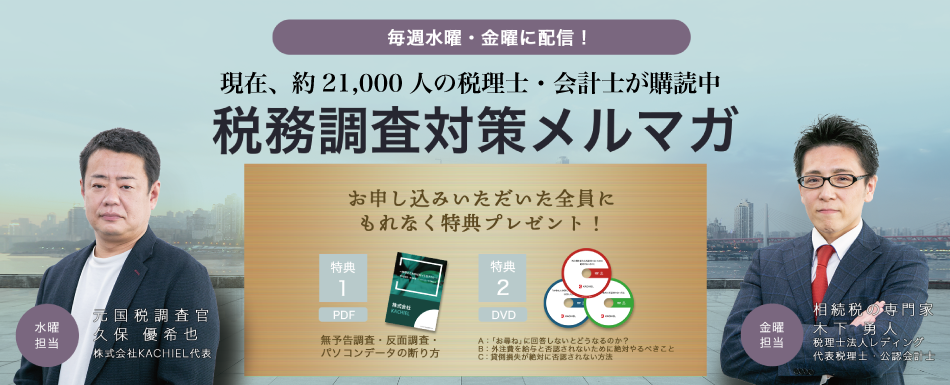取引相場のない株式評価に関する検討(1) ~純資産株価~
※2024年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「取引相場のない株式評価に関する検討(1) ~純資産株価~」です。
今回から数回にわたり、
純資産株価の検証をしていきたいと思います。
取引相場のない株式評価については
財産評価基本通達
178 取引相場のない株式の評価上の区分
から
189-7 株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正
までで、定められています。
また、個別通達として
平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における
取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式及び記載方法等について」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/07.pdf
が定められています。
この個別通達については、
以下、評価明細書通達といいます。
純資産株価算出にあたり、実務上で問題となるのが
1.仮決算方式
2.直前期末方式
ではないでしょうか。
本来、原則となるのは
1.仮決算方式
ですが、
評価明細書通達「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
2(4)では、以下を定めています。
―――
(4)1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算は、
上記(1)から(3)の説明のとおり課税時期における
各資産及び各負債の金額によることとしていますが、
評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、
課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、
直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について
著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、
課税時期における各資産及び各負債の金額は、
次により計算しても差し支えありません。
このように計算した場合には、第2表の「2.株式等保有特定会社」欄及び
「3.土地保有特定会社」欄の判定における総資産価額等についても、
同様に取り扱われることになりますので、これらの特定の評価会社の
判定時期と純資産価額及び株式等保有特定会社のS2の計算時期は
同一となります。
イ「相続税評価額」欄については、
直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額
ロ「帳簿価額」欄については、直前期末の資産及び負債の帳簿価額
(注)
1 イ及びロの場合において、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、
次の金額は、 負債として取り扱うことに留意してください。
(1)未納公租公課、未払利息等の金額
(2)直前期末日以前に賦課期日のあった固定資産税及び
都市計画税の税額のうち、未払いとなっている金額
(3)直前期末日後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額
(4)被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが
確定した退職手当金、功労 金その他これらに準ずる給与の金額
2 被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合には、
その生命保険金請求権(未収保険金)の金額を「資産の部」の
「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。
―――
つまり・・・
「評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、
課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、
直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について
著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるとき」は、
2.直前期末方式
が認められることになります。
また、評価明細書における
資産の部の「帳簿価額」は
「資産の部」の「相続税評価額」欄に評価額が記載された
各資産についての課税時期における税務計算上の帳簿価額
を記載します。
また、評価明細書における
負債の部の「帳簿価額」は
「負債の部」の「相続税評価額」欄に評価額が記載された
各負債の税務計算上の帳簿価額をそれぞれ記載します。
つまり・・・
会計上の帳簿価額ではなく
税務計算上の帳簿価額を採用することになります。
そのため・・・
別表5(1)で留保されている加減算項目の
調整が必要になることを意味します。
次回からは、
「2.直前期末方式」
「税務計算上の帳簿価額」
を採用することによる実務論点
を複数整理していきます。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報