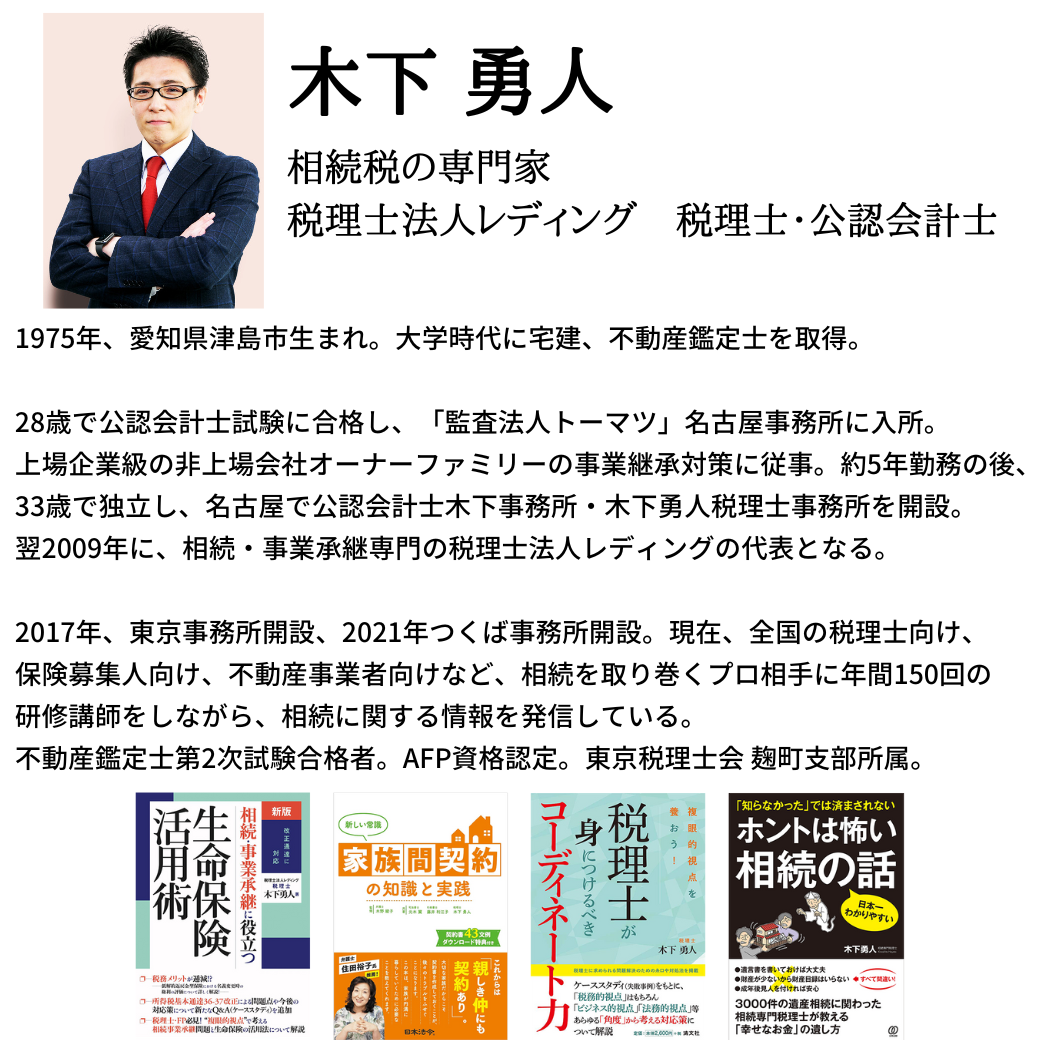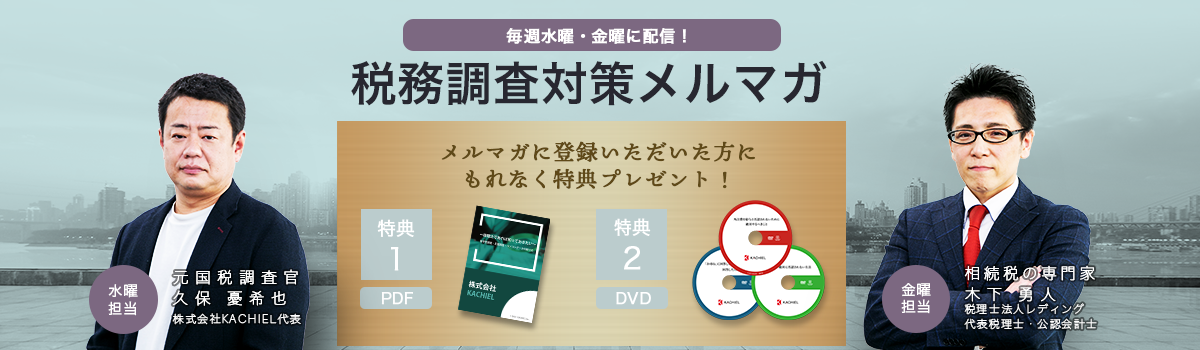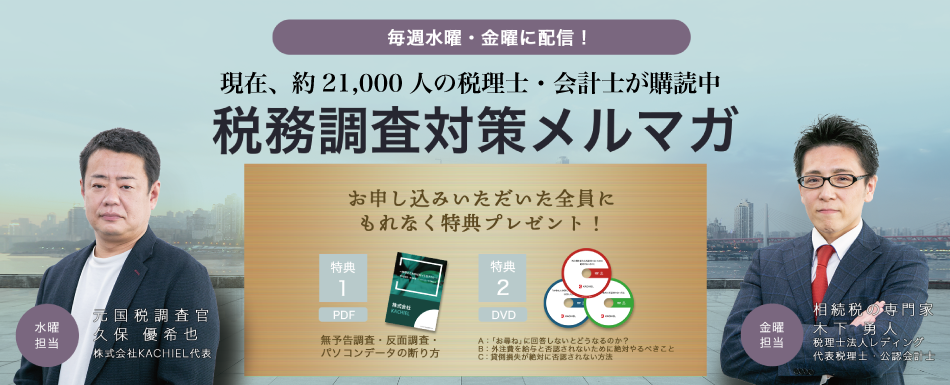役員解任に関するリスク検討
※2024年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「役員解任に関するリスク検討」です。
ある社長からのリアル相談です。
社長:
先生、今年6月頭に役員に就任させた〇〇ですが、
ポテンシャルを見誤っていたようで。
役員を辞めさせたいのですが、
役員を解任することはできますか?
私:
株主総会の普通決議で解任することは
会社法339条、341条にて認められています。
持株割合は
社長8割
奥様1割
〇〇さん1割
ですので、問題なく解任決議できます。
つまり・・・
過半数の出席(定足数)
出席株主の過半数の賛成
で解任決議できることになります。
1割しか保有しない〇〇さんが賛成しなくても
解任できるということです。
ただし、もし可能であれば・・・
〇〇さんに辞任届を提出してもらった方が
穏便にことが進むと思います。
社長:
それがね、先生・・・
〇〇本人が辞任する意思が全くないんですよ。
だから・・・
強制的に解任させようと考えたという訳です
私:
わかりました。
実際に解任を進める前にいくつか確認させてください。
■確認1
定款を確認させてください。
(理由)
確認事項として、役員の任期があります。
会社法332条1項で2年と定められていますが、
・定款で短縮すること(同条同項ただし書き)
・定款で10年まで伸長すること(同条2項)
が可能となっています。
任期まで短いのであれば、任期満了まで待つという
選択肢が出てきます。
会社法上の公開会社でない株式会社であれば
10年まで伸長していることも最近では多いです。
社長の会社は任期を伸長していませんでしたので、
現在8月ですから、残り1年10か月あります。
任期満了まで待つのは厳しいと考えるか否か。
となると、〇〇さん本人に辞任の意思が無ければ
解任も止む無しとなるかと思います。
■確認2
解任のリスクを理解してください。
(理由)
株主総会の普通決議で解任することは可能ですが、
1.損害賠償請求の可能性
2.「解任」登記を見た取引先や金融機関からの
信用不安
3.営業機密漏洩等の可能性
があります。
1.損害賠償請求の可能性
を詳しく説明します。
—
会社法339条(解任)
2.前項の規定により解任された者は、
その解任について正当な理由がある場合を除き、
株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を
請求することができる。
—
(1)正当な理由がある場合
こちらの判断基準を裁判所が整理しています。
・役員の不正行為や法律違反を理由に解任する場合
→ 正当な理由あり
・役員による経営の失敗あるいは経営能力の不足、
株主との経営方針の相違を理由に解任する場合
→ 正当な理由ありと認められにくい
(2)損害賠償請求額
正当な理由がない場合には、
会社側は損害賠償責任を負います。
過去の裁判例を確認すると
「解任された取締役(役員)が、
任期満了まで役員を勤めた場合に
受領できたはずの役員報酬の総額」
とされることがほとんどではないかと思います。
—
大阪高裁昭和56.1.30
その損害の範囲は、取締役を解任されなければ
残存任期期間中と任期満了時に得べかりし利益(所得)の
喪失による損害を指す
—
具体的には、
「解任時の役員報酬の月額」
× 「解任から任期満了までの月数」
となります。
〇〇さんの報酬は
定期同額給与として1,200万円ですので、
月額100万円×22か月=2,200万円
という損害賠償請求が起こされる可能性があります。
この場合に、会社側が支払った損害賠償金につき、
給与対価としての源泉徴収が必要か否かに関する
文書回答事例がありますので、以下ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/index.htm
結論としては、以下のとおりです。
1.損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる
役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に
基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎない
2.損害賠償金は、給与所得ではなく対価性のない
一時の所得として一時所得に該当すると考えられるため、
会社はその支払の際にこれを役員報酬(給与所得)として
源泉徴収を行う必要はない
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報