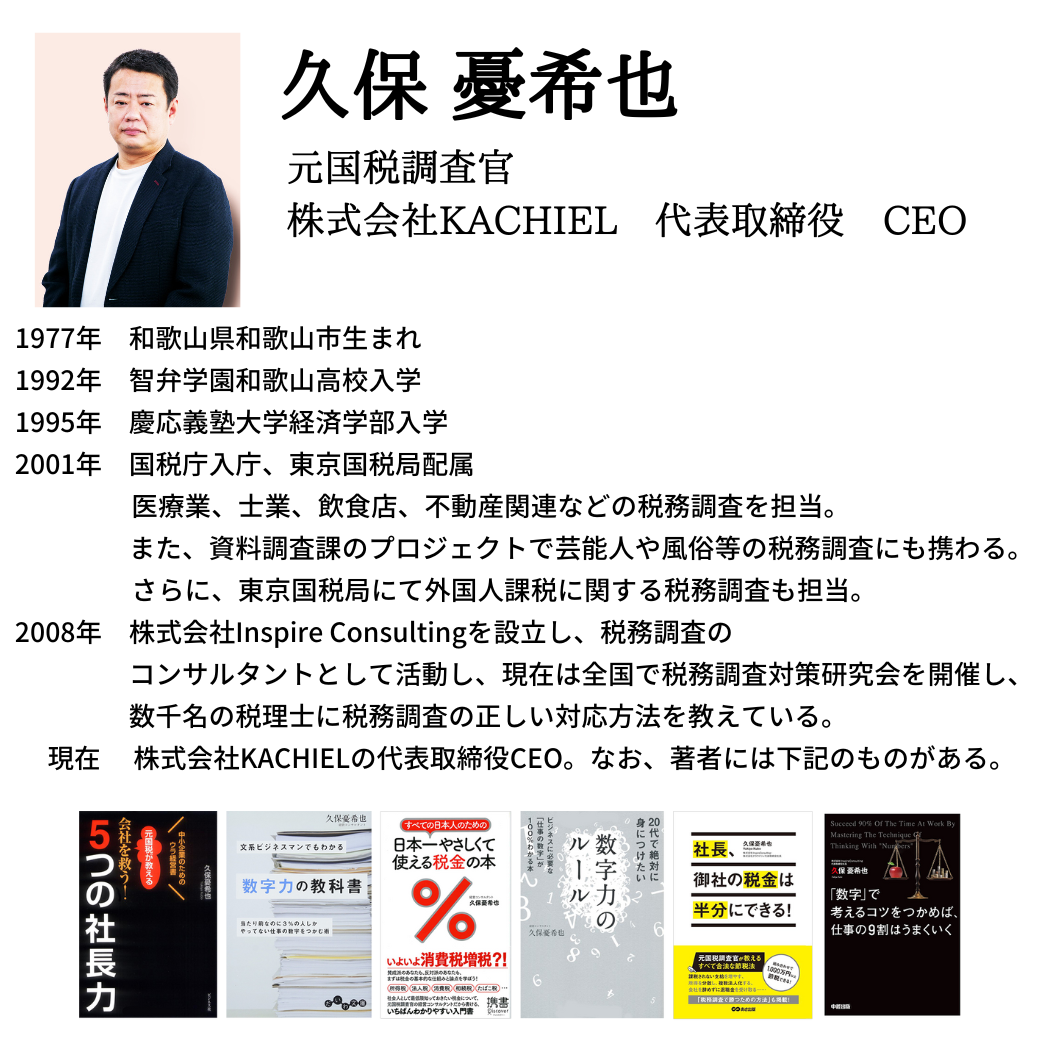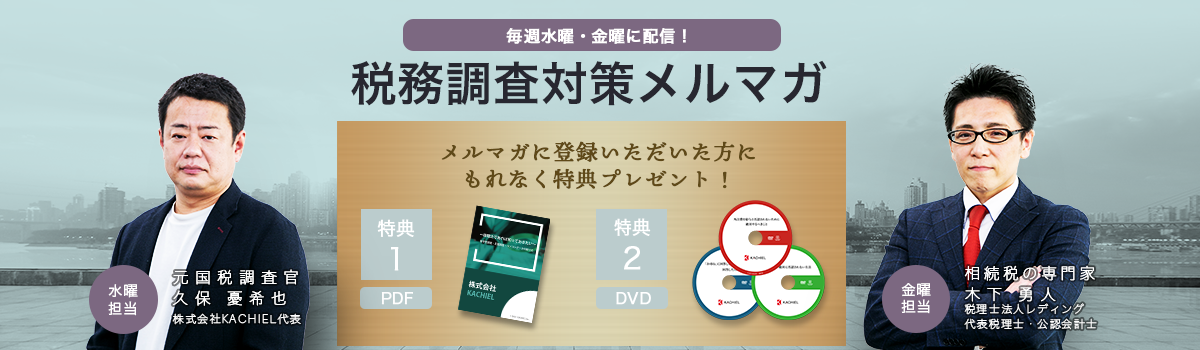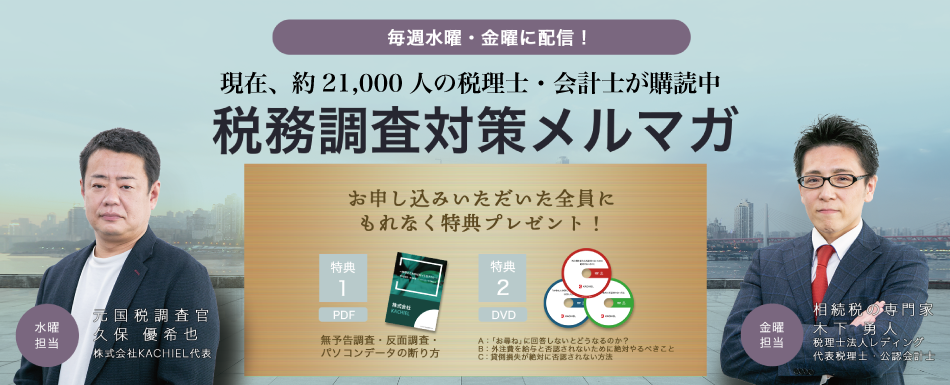重加算税を体系的に理解する(税目をまたぐ場合)
※2024年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
毎週水曜の本メルマガでは連載で「重加算税」について
解説していますが、今回は法人税・消費税・相続税など
複数の税目をまたぐ場合の重加算税を取り上げます。
原則的な考え方ですが、隠蔽・仮装行為があり、
2つの税目において修正申告を提出するケースでは、
両税目に重加算税が課されることになります。
わかりにくいので典型例を挙げると、
法人税・所得税で売上除外=重加算税となる場合、
連動する消費税にも重加算税が課されることになります。
この点は、事務運営指針にも明記されています。
「消費税及び地方消費税の更正等及び
加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/000703/01.htm
第2 Ⅳ 2(所得税等に不正事実がある場合)
所得税又は法人税(以下「所得税等」という。)につき
不正事実があり、所得税等について重加算税を
賦課する場合には、当該不正事実が影響する消費税の
不正事実に係る増差税額については重加算税を課する。
一方で、上記原則的な考え方から外れる場合として、
法人の経費のうち社長個人の私的支出があったなど、
法人税側で役員賞与と認定され損金不算入、併せて
給与課税となった源泉所得税については、二重に
重加算税が課されないこととされています。
「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/02.htm
第1 4(認定賞与等に対する重加算税の取扱い)
(略)法人税について重加算税が賦課される
場合において、法人税の所得金額の計算上損金の額に
算入されない役員又は使用人の賞与、報酬、給与
若しくは退職給与と認められるもの又は配当等として
支出したと認められるもの(以下「認定賞与等」という。)
の金額が当該重加算税の計算の基礎とされているときは、
原則として、当該基礎とされている認定賞与等の金額のうち、
当該重加算税の対象とされる所得の金額に達するまでの
認定賞与等の金額については、源泉所得税及び
復興特別所得税の重加算税の対象として取り扱わない。
なぜ法人税と源泉所得税は二重課税にならないのか、
おそらくそこに論理はないものと推察しますが、
納税者有利の規定ですから、知っておくべきでしょう。
認定賞与と事実認定された場合、一般的には
法人税=重加算税/源泉所得税=過少申告加算税
となりますが、繰越欠損金等があり法人税において
増差所得・税額が発生しない場合は、源泉所得税で
重加算税が課されることになります。
また、税目がまたぐ可能性があるケースとして、
法人における株価と相続税・贈与税の関係があります。
例えば、創業者が保有する株式を子・孫に
生前贈与をしているケースで考えると、
法人において隠蔽・行為があり(法人は重加算税)、
株価が@5,000円から@8,000円になったような場合、
新たに発生する贈与税には重加算税が課されます
(正確には、事務運営指針に明記されていないので
原則に基づき重加算税が課されるものと考えます)。
一方で、被相続人である創業者(大株主)が
生前に法人で隠蔽・仮装行為を行っており、
税務調査で法人に重加算税が課されたとしても、
跳ね返った株式の評価額(増額分)に対して
重加算税を課されることはないでしょう
(あくまでも、相続人が法人経営に
参画していなかったことを前提としますが)。
これは、あくまでも相続人が隠蔽・仮装行為を
行ったわけではなく、被相続人の行為であることから
重加算税は連動しません。事務運営指針においても、
相続税の隠蔽・仮装行為の主語は「相続人等」
とされていることからも理解できるかと思います。
「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm
さて、来週水曜の本メルマガでは、事務運営指針に
規定されている「消費税固有の重加算税」の論点を
複数取り上げて解説します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報