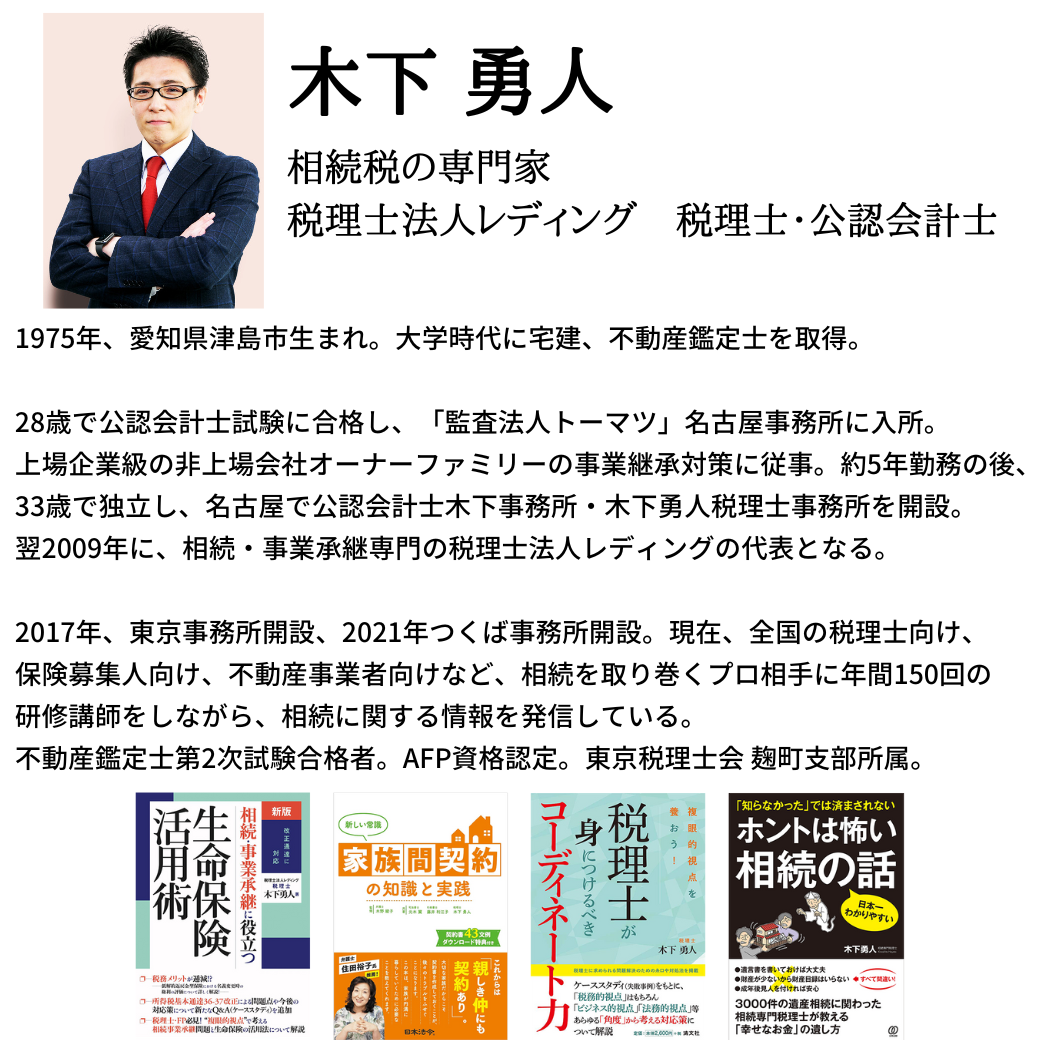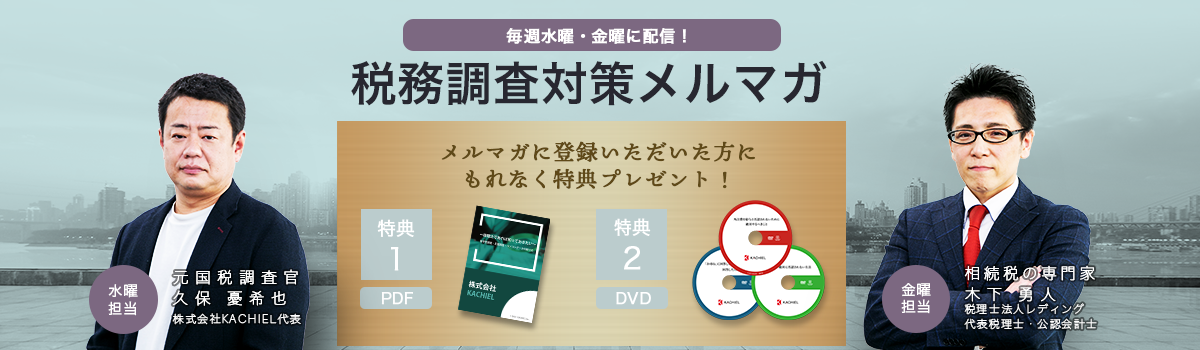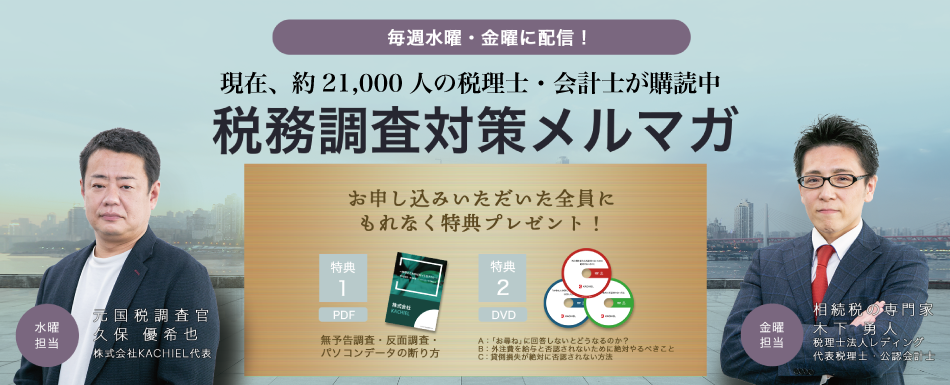取引相場のない株式評価に関する検討(5) ~純資産株価~
※2024年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「取引相場のない株式評価に関する検討(5) ~純資産株価~」です。
前回は、相当の地代に満たない地代を収受している場合
における純資産株価を検証しました。
今回は前回に引き続き
相当の地代を収受している場合における借地権計上を検証しますが、
非常によく間違える盲点を取り上げます。
以下の例は「被相続人」「株式所有者」「会社規模」以外は
前回と全く同様です。
例:
土地所有者:個人(社長)
建物所有者:法人
借地権の設定:平成15年
無償返還届出:未提出
評価対象地の借地権割合:60%
通常の地代:240万円
相当の地代:600万円
実際の地代:600万円
土地の自用地価額:1億円(※)
※ 借地権設定時から不変
権利金の授受:無
被相続人:社長の配偶者(妻)
株式所有者:社長60%、妻40%
会社規模:小会社
(1)借地権設定時
こちらは前回と同様のため、割愛させていただきます。
結論としては、権利金の認定課税は回避されます。
(2)被相続人の相続発生時
今回、盲点になりやすいのは、相続発生時における
借地権になります。
貸宅地が自用地評価額の80%という部分については
特に間違えにくい箇所になりますので、こちらは割愛します。
前回と異なる箇所は、
「被相続人」
「株式所有者」
「会社規模」
になりますが、特に注意すべきは
「被相続人」
「株式所有者」
となります。
前回の設定では、
被相続人:社長
株式所有者:社長100%
となっていたものが今回は
被相続人:社長の配偶者(妻)
株式所有者:社長60%、妻40%
となっています。
この違いが何をもたらすことになるのでしょうか。
結論から申し上げると、
純資産価額に算入される
借地権2,000万円の計上は不要となります。
理由は以下のとおりです。
個別通達:
相当の地代を支払っている場合等の
借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
6 相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価
―――
(注) 上記(1)及び(2)のただし書に該当する場合において、
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し
土地を貸し付けている場合においては、
昭和43年10月28日付直資3-22ほか2課共同
「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達
(以下「43年直資3-22通達」という。)の
適用があることに留意する。
―――
こちらは前回でも根拠にした個別通達になりますが、
「被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し
土地を貸し付けている場合においては、」
となっていることに注目してください。
つまり、
借地権20%計上するための前提条件になります。
これを本ケースに当てはめます。
被相続人(社長の配偶者(妻))が
同族関係者となっている同族会社に対し
土地を貸し付けて「いない」
のです。
土地を貸し付けているのは、あくまで
社長であり、社長の配偶者(妻)ではないのです。
そのため、前提条件を満たさないことになり
純資産価額への借地権20%の計上は不要となります。
今回、会社規模を「小会社」にしたため、
純資産価額50%を使用する必要があるため、
社長の配偶者(妻)が保有する自社株40%の評価に
大きな影響を及ぼすことになります。
もちろん、会社規模が「大会社」であれば、
特定の評価会社に該当しない限り、
純資産価額は株価に影響を与えないことになります。
次回は、相当の地代に満たない地代を収受している場合
における純資産株価を検証します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
著者情報